- blog
- album
- (089)-952-1777
- mituba@mituba.net
幼稚園の日記(ブログ)
2024年3月14日 木曜日
今日の卒園式の練習終わりになにやらぞう組の女の子が古森先生に相談していました。相談し終えるとマイクをもらい、「さき先生、私たちに時間をください」と言いました。すると、それが他のクラスの子達にも伝わり、らいおん、きりん、くま組の子達が次々に担任に「クラスから出て、4人でどこかで休憩していて下さい」と言いました。私たち年長教師4人は一体何が起こるんだろう?「練習するのかな?」と思いつつも約束の12:15に部屋から出ました。するとどこかのタイミングで誰かが”先生にプレゼントを作ろう“という提案をしたこと、それを4クラス100名以上の子達に子どもだけの力で伝達し、意識統一をしていたようで各クラス想いの詰まったプレゼント作りが開始しました。様子を見にきた事情を知っていて一番の理解者の古森先生や丸山先生、同じフロアに居る年中の西森先生を上手く巻き込み、「大きい段ボールない?」「頭の大きさが分からないから先生頭貸して」「ちょっと先生手伝って」とみんなで知恵を絞り、役割分担をし、今までの経験を活かしてクラスで作り始めました。
手紙の内容をみんなで考えて書くクラス、三葉っこと言えば廃材!廃材を工夫してみんなと協力し作るクラス、絵を描いて想いを伝えようとするクラスなどそれぞれみんなで「時間がない!」と急ぎつつ完成させてきました。そして12:50 会議室に呼ばれて行くと次々と4クラスの子ども達がマイクを持って進行し、プレゼントを渡してくれました。ここまで自分達で考え、発言して、友達と協力してやり遂げられる子ども達の姿にとても感動し、ここまで育ってくれているんだなと卒園を前に胸が熱くなりました。こんなにもいい子たちに育ったのは保護者の方々、地域の方々、周りの方々、一緒に過ごしてきた仲間のおかげだなと強く思い、一緒に過ごすことができて幸せだったなと思いました。こんなステキな子ども達と生活できた1年間、この仕事の素晴らしさ、喜び、感動、全てを卒園式2日前の今日、子ども達が教えてくれました。
2024年2月28日 水曜日
今朝も、本園の園庭では寒さを吹き飛ばすように体を動かして遊んでいた子供たちがいました。すると縄跳びをしていた年長児が「先生、跳んでみて」とくま組のT先生に縄跳びを渡しました。T先生は「できるかな…」と二重跳びを跳んでみると結果は一回!「えぇ〜!」っと少しがっかりそうな子供たちは、次にきりん組のK先生に声をかけ、やってもらうとまた一回。らいおん組のI先生は7回跳べて「おぉー、他の先生にもチャレンジしてもらおう!」と事務所にいたM先生やバスに乗っていた年少のK先生、N先生、三葉幼稚園の1番若いF先生。そしてバスを運転していたM先生にも声をかけ、急遽先生のなわとび大会が始まり、年長児たちは大盛り上がりです。そんな中きりん組のAちゃんは「じゃあ、1番多く跳べた人には賞状と一万円あげる!」といって早速作り始めました。
子供たちの中には「まだ、O先生とN先生がまだ帰ってきてない」「N先生の方が跳べそう!」「いや、O先生だよ!」と予想をしたり、参加させられた先生達もこの子どもたちが開催したなわとび大会に本気で跳んで悔しがり、競技記録は1回目のものとするルールだったにもかかわらず、そのあとも「いや、もうちょっと跳べるはずだからやらせて!」と何回も挑戦する先生が続出していました。その様子も子ども達は楽しそうに、見守ってくれていました(笑)そうしていると先にO先生が帰ってきて早速チャレンジです。すると今までの最高記録M先生の12回をこえ、1回目の挑戦で19回も跳べ、「すごーい!」と歓声が上がり、その後のN先生は19回には届かず今日の優勝者はO先生となりました。子ども達もこの朝の時間でなわとびをする子が沢山いて、大人も子どもも全力で遊んでとても楽しい時間となりました。
たくさん遊んだ後は年長児は残り2回となった手話教室がありました。今日は新しい「ともだちになるために」の手話を教わり、残りの時間は今までの復習の時間となりました。
そして、昨日、年少・年中さんが病児保育園の見学ツアーをしたと聞いて「いいなぁー」と羨ましがっていた年長児達と見学を兼ねてさんさんらんどへ遊びに行くことにしました。この病児保育のステキな部屋は「みんなが来年一年生になっても病気になったらここに来れるからね」と話すと「安心だね!」「絶対そうするね」「じゃあママはお仕事休まなくていいんだ〜」とその意味をしっかり理解している子もいて驚かされました。年長児達は「また、幼稚園に来れるってことかぁ」と嬉しそうに言いながら見学していました。
仮園舎にいる年少さんやたんぽぽさんとはなかなか一緒に遊ぶ時間が取れなかったので今日は年少さんたんぽぽさんも園庭に出てきてくれて遊ぶことが出来ました。バスが一緒で顔見知りの子や普通はなかなか遊ぶ機会のない小さなお友達など誰にでも優しく手を差し伸べて山を上ったりおりたりしながら短い時間でしたが、遊ぶことが出来ました。卒園までさんさんらんどで遊べる回数も、年少さん達と関われるのも幼稚園での生活全ての時間が1日1日少なくなってきていることを年長児達は実感していて「早く一年生になりたい〜」「幼稚園にもまだ来たい〜」と年長児達は教師に聞かれる度に手を挙げたり下げたり、可愛い姿が見られます。教師達も同じ気持ちです。今後の一回一回を大切に過ごしていきたいなと思います。
コメント (「なわとび大会!?」 らいおん組今岡美奈穂 はコメントを受け付けていません)
2024年1月15日 月曜日
今日は年長、年中組の青コースがアイススケートに行きました。子どもたちは朝からワクワクドキドキ!!さぁバスに乗っていざ出発です。バスの中でもとっても元気でワクワク感が収まりません。しかし、このバスの時間はとっても大切な時間で行ってからのお約束事が沢山あるのです。まずはスケート靴のはきかたからです。年長児たちは年中の時の事をよく覚えていて、教師の問いかけにどんどん答えていました。一通り大事なことを話し終えたところで一緒に乗ってくれていた園長の「どうして手袋をつけないといけないの?」とクイズが始まりました。「うーん、手がつめたいから」「しもやけができるから」と次々でてくるとYちゃんが「違う!靴の下に包丁がついとって、手を踏まれると切れるんよ!」と説明まで付けて答えてくれました。昨年アイススケートに行った時の注意を覚えていたのです。流石です。三葉の年長児の凄いところだなと思いました。「そうだよね!手が切れないように守るために、手袋がいるんだよ。手の他にも守らないといけないところはどこかな」とまたクイズが出ると「あたま!ヘルメットで守る!」と答えていました。そして「らいおん組さんは先生好き?」の質問に『うん!!』と元気に返事が返ってきました。「でも、先生のところにくっついたらいけないよ。先生たちもあんまり上手じゃないから転んじゃうとぶつかるからね」と話していると園長が最後に「みんな赤ちゃんのときはハイハイから始まって自分の力で立って歩けるようになったんだよね。だから今日も大丈夫!みんな先生にくっつかないでも、自分の力で立って自分の力で歩くの頑張れるよね。」と励ましてもらったことでさらにやる気満々になったところでちょうどイヨテツスポーツセンターに到着です。着いてからは役員さんにスケート靴を履かせてもらってリンクに入るとインストラクターの方に立ち方や転んだ時の注意点など話してもらい、いよいよ自由時間です。年長児たちは去年の経験もあることから立ち上がるのが早く、とても上手に転んでは立ち上がってヨチヨチ歩いたり、少し慣れてくると、すいすい~と滑ったりしていました。
年中さんもたっぷりと時間をかけて小リンクで練習したあと大リンクに移り、みんな楽しんでいました。
1時間たっぷり時間をかけて遊んで最後は各クラスリンクの反対側から園長の「よーい、どん!」で滑り始めました。リンクの端から端まで転んでも諦めずにみんなが園長の前まで進んでゴールすることが出来ました。帰るバスの中でも「また行ける?」「明日も行きたーい」と満足気に降園していました。
アイススケートに行って、子どもたちはあきらめず自分の力で頑張ってできるようになる楽しさを味わうことができて良かったなと思います。残り3ヶ月もたくさん楽しんで色々なことに挑戦し、友達と切磋琢磨しながら小学生になるという期待を胸に成長してほしいと思っています。
コメント (「アイススケートに行ってきたよ」 らいおん組 今岡美奈穂 はコメントを受け付けていません)
2023年12月15日 金曜日
昨日の夜から降っていた雨のおかげ?で、さんさんらんどの園庭には大きな水たまりが出来ていました。登園してきた年中、年長児はこの時にしかない自然の贈り物の水たまりを使って泥あそび、そして水たまりの上を跳びこえるジャンプのあそびなどで盛りあがっていました。軽く助走をつけ、一番大きな水たまりをジャーンプしたTくん。あっ!と思った瞬間に着いた右足はギリギリの所で水たまりの中に入り、ヒヤッとする場面もありながら、楽しんでいました。
そして、今日年長児は3学期にある発表会と、卒園に向けての準備や話し合いなど、各クラスで活動をしました。発表会に向けては、きりん組は第二園舎の2階の図書室にあがって面白そうな絵本を探して読み、くま、らいおん、ぞう組も子どもたちが持ってきてくれた絵本を読みました。らいおん組は絵本を2冊選んで読み、子どもたちがきいていてより楽しかったと思った方の絵を描いてみることにしました。するとたった1回しか読んでいないのに、「ここがおもしろかった!」「顔が怖いんよねぇ~」と印象に残った場面をリアルに描いていました。帰る前にみんなで描いた絵を集めて絵を見ながら紙芝居のように話してみました。すると、ノッてくる子がたくさんいて、子どもたちと「次はどうなるの?」「のみこまれる!」などといいながら進めていくことができました。子ども達のたのしかった場面を絵に描いていたのでストーリーの中には欠けている場面もありましたがなんとか、まとめることができました。他のクラスも劇にしたい絵本を見つけて自分の好きな場面を絵に描いて、物語を振り返って親しんでいました。2学期も残りわずかですが、子どもたちと3学期の最大行事、発表会と卒園式を意識しながら活動していきたいと思います。
また、今日明日と個人懇談もあるので子どもたらと部屋の片付けをした後、年長児は懇談に来られたお母さん方にお店やさんの雰囲気も味わってもらおうと各おみせで余っている商品を用意しているとさすが何度もお店やさんをひらいてきた子どもたちです。手際よく並べ、協力し合って部屋の準備をしていました。明日は子どもたちと準備した部屋で保護者の皆様とお話できるのを楽しみにお待ちしております。
コメント (「みんなで頑張るぞ!」 らいおん組 今岡美奈穂 はコメントを受け付けていません)
2023年10月12日 木曜日
今年度の運動会を屋外遊ぎ場ですることが決ったのは、9月に入ってからでした。それまで園外に会場を探しては、練習はどうするか思案の毎日でした。そして、屋外遊ぎ場に何とか子どもが活動できる広さを確保できることが分かり、本格的に練習が始まったのは9月中旬頃からでした。私は間に合うだろうかとひやひやしながら、練習方法を考えていました。
そして、練習を始めるとついつい焦って口うるさくなってしまい、後味が悪い思いをしていたのですが、それを見た園長は「大丈夫よ。昨日よりもここが良くなった。」と、その都度褒めてくれると、子ども達の表情も動きも変わってきました。運動会まで残り一週間となった今週は、月曜日から園長も毎日練習に加わってくれ、少しずつ課題をもって修正してきて、子ども達も生き生きと練習を進めています。そして、今日も復習からスタートです。
鼓笛隊の旗の子たちは、月曜日からずっと数を数えること、かっこよく歩くことを課題にしてきました。一発目の練習では、まぁそれなりに動けていますが、まだまだ統一感がありません。それを見て園長も「みんなは誰に見せるために鼓笛をするの?見に来てくれるお父さん、お母さんのためだよね。みんな昨日よりもかっこよくなってるんだけど、もっとできるはず!数を数えて、声をそろえて、気持ちをそろえて、一つになって、今日一番頑張っているところを見せてね。」そして、今日はいつも自分たちのためにたくさん(口うるさく)指導してくれる担任の先生に見てもらうために「頑張ろう!」と、意気込んでスタートです。少し張り切りすぎて先走って動いてしまうことはありましたが、声を出してかっこいいところを見せようと、真剣に頑張っている姿がありました。まだまだ各パートごとに課題はありますが、毎日少しずつかっこよくなっていく子どもたちの姿に、特に今日は感動し、こんなにもみんなが揃ってできるのかと驚きました。声の掛け方や指導の仕方(特に良い所を褒めることで、教師の求める所を分からせること)が大切なことを園長の指導の仕方で教わりました。あと三回しか練習はありませんが、ポイントを押さえ、このかっこいい姿を保護者の皆様に見てもらえるよう、良い所を褒めながら練習していきたいと思いました。
一日一日子ども達の成長が見えて、楽しみです。
コメント (「一歩一歩、課題を乗り越えるぞ!」 らいおん組 今岡美奈穂 はコメントを受け付けていません)
2023年7月19日 水曜日
今日は年長児4クラスで駐車場のキュウリを収穫しに行きました。実は園長からキュウリを出来るだけ大きくなるまで待って少し色が変わる頃に収穫するように言われていて、今日が待ちに待ったその日なのでした。集まると、野菜クイズが始まりました。1問目はキュウリの花の色です。みんなで目の前のお花を見ないよう目をつぶって「①赤、②黄色 さあどっちでしょう!」ときかれると、自信を持って”2番!!」と答えていました。そして2問目です。「キュウリの葉っぱは触るとどんな感じでしょう!①ふわふわ②ちくちく③ぬるぬる」というクイズには答えが分かれました。「正解は①と②でした!」『えぇ~』と楽しくクイズをした後、今日はなんと10本のおおきなキュウリが収穫できました。みんなの収穫したキュウリとその時に一緒に収穫したトマトのリリコは氷水の入った大きなタライの中で冷やしておき、その間に、ペットボトル水鉄砲をして体をたくさん動かし、走り回って楽しみました。
散々遊んだあと、水着のままテラスの前に集まった子ども達は古森先生が出てきてくれるとわくわくと期待のまなざしを向けます。そこには先ほど収穫して冷やしておいたキュウリがありました。先ほど収穫した大きなキュウリと普通のサイズの2種類のキュウリがみんなの前に並べられ、古森先生が「みんな見てて、こんなーに大きくなったキュウリの中と小さいキュウリの中どんな違いがあるか切ってみるよ〜」と言いながらキュウリを縦に包丁を入れてみせてくれました。すると「あっちがう!」「大きいのはたねがある!」と気付いたことを口々に、よく聞いていて反応していました。割ってみたキュウリの中身は小さい普通のキュウリはたねが大きくなっておらず、大きくなるまで待っていたお母さんキュウリのたねは大きく、かたくなっているのがよく分かりました。そしてこのお母さんキュウリは白くて…とっても美味しそうに見えました。
でもそのまま食べるのではなく、「みんなは今たくさん動いて汗かいたね。汗にはお水とお塩が入っていてしょっぱいんだよね!という事はみんなの体の中からお水とお塩がなくなってきたので、そんなみんなの体に今必要なのはお水とお塩だね。そこでこのきゅうりでみんなの体の中にキュウリのお水とお塩を返してあげるんだよ~」と楽しくて不思議な話をしてくれました。そしてキュウリを切るときにもまた1つ美味しくなる方法を教えてくれました。それは「大きくなりすぎたお母さんキュウリの皮はかたいので皮を剥きたいけど…皮にも栄養があるからこうやってしゅるっとしゅるっとしましま模様に皮をむいて皮も残すんだよ。しましまにすると栄養もとれて皮も食べやすくなっておいしいんだよ」と話をしながら、古森先生の手は止まらず動きつづけます。その様子をじーっと見つめる子ども達。大きめに切られたキュウリを見てT先生やN先生たちが「これとこれとこれとこれ、私のやつ!」と茶々を入れると『ダメー!!私のも!それ〇〇の!」と子供達の悲鳴が上がります。そしてボールに入った半月の形の厚めに切ったキュウリに魔法の粉(塩)を入れると、古森先生がボウルを振ってキュウリをころころと転がして、塩がキュウリ全体にかかるように器用に動かしていきました。そのリズムに合わせて子ども達も自然と『1、2、1、2.』とかけ声をかけます。そしてキュウリの塩ころがしのキュウリが完成すると味見をさせてもらいました。薄塩のキュウリは少し甘さも感じられ、口に入れた瞬間の子ども達の表情…なんともかわいらしく顔が溶けそうなほど満面の笑みで「おいしい~」と食べていました。あんなに野菜が苦手なSちゃんも「おいしい」とペロッと食べていて、みんなで食べるこの時間の大切さを感じました。そして今日は塩ころがしだけでなくみんなの育てていたトマト、そして1本だけできていたナスも食べることができました。ナスは塩ころがしではなく、塩をもみこんで水分を絞る調理法をみて、『ナスよしよししてる!』そしてぎゅーっとしぼると水がタラタラ〜っとたくさん出てきました。「うわーすごい。」と子供達が命名のナスの”塩よしよし”の調理法のナス料理を食べることができました。更にキュウリの塩ころがしだけでなくお酢で味付けしたものも加わり、全部で4種類のお野菜料理を食べることができました。どれもとっても美味しかったようで「もっと食べたい」「おいしい」と大喜びの子どもたちでした。水鉄砲を終え、水着姿で夏の野菜をほおばる子どもたちの姿はとってもかわいかったです。そして年中、年長だけでなく、たんぽぽ黄組や保育園のもも組さんも太めに切ったキュウリの塩転がしおいしくてぺろっと食べ、おかわりをねだるほどだったそうです。その時期、その時期に旬のものをタイミングよく味わわせていきたいなと思いました。
コメント (「夏野菜ってサイコー!!」 らいおんぐみ 今岡美奈 はコメントを受け付けていません)
2023年6月5日 月曜日
今日は年中さんと年長さんが秀野邸に、年少さんがポンタ農園に、そしてたんぽぽさんは駐車場に行きじゃがいもと玉ねぎの収穫をしました。
<年長、年中>
始めに北斎院町の畑に到着した年長児は畝に入っていき、じゃがいもの掘り方について話をききました。教師が「じゃがいもは誰が植えたの?」と聞くとここのじゃがいもは自分たちが植えたことを自信満々に答えていました。じゃあ、何を植えたの?という質問に「種?ちがう…」と首をかしげながら少し不安そうに答えていました。なんとなく違っていることに気付き、何だったっけと考えていたので少しヒントをあげると「あー!じゃがいも切ってお薬つけた!!」と思い出すことができました。過去の自分達の経験をこうした機会に振り返ることで何度も復習し覚えていくんだなと私自身学んだ時間でした。そうして植えたことを振り返ったあと、1株みんなの前で掘ってみるとお母さんにつながった赤ちゃんたちがたくさん出てきました。それを見た子ども達は「わぁ〜ぎゅーっとしてるみたい!」とかわいらしい感想が出てきました。お母さん芋が頑張ってくれたからこんなにたくさん子どもが出来たこと、緑色になっているじゃがいもは毒で、どうしてそうなったのか等の話をきいて、「じゃがいもをたくさん見つけるぞー!」「おー!!」と気合十分においも掘りがスタートです。
そのあと年中さんもやってきて話をきいたあとみんなでおいもを掘り、玉ねぎを収穫しました。あちらこちらで「ここ手伝おうか!」「〇〇ちゃんが一緒に掘ってくれたから大きいの掘れたんよ」と協力して掘っている姿が見られ三葉の子たちだからだなと嬉しくなりました。また、玉ねぎを収穫するときには根がなかなか抜けないと困っていたK君を見て、A君がすかさず助けに入ります。その姿が大きなカブのお話しのようでとってもかわいらしかったです。他にもとれたじゃがいもを抱えきれず、一つ持ったら一つ腕の中からこぼれ落ち、何度も拾いあげていたS君を見て、G君が「半分もつよ!かして」とサラっと言ってかっこよく手伝ってあげている姿などいろいろな姿が見られ、とっても楽しいあっという間のじゃがいも掘りでした。放課後には「当たり前のように年長児がじゃがいもの仕分けを手伝っていて、「三葉っこたちの頼もしさを感じる1日となりました。また収穫したじゃがいも、玉ねぎを給食のメニューで食べれるのも楽しみにしている子どもたちです。
〈年少〉
年少4クラスはポンタ農園に行きました。じゃがいも掘りを楽しみにしていた子ども達は、ポンタ農園に歩いていく道中も「大きなじゃがいも掘れるかな~。」と楽しみでいっぱいです。
ポンタ農園に着くと、世話をしてくれている藤岡さんと田中さん、そして看板犬のポンタ君が出迎えてくれ、子ども達も元気よく挨拶をしていました。
ポンタ農園に行くと毎回思うのですが、空気がおいしく、緑がいっぱいで世界が変わります。トウモロコシにきゅうり、なすびにピーマン!!みかんにもも、沢山の野菜や果物が力強く育ち、モンシロチョウが子ども達が来たのを喜んでくれるかのように寄ってきてくれました。そして、今日子ども達が一番驚き、興味を持ったのは、H君が「へびだー!!」と驚くほど大きなミミズです!!私もこんなに大きなミミズを見たのは久木ぶりです。ミミズさんが土をフカフカにしてくれていることを知ると「ミミズさんがありがとう!」と言う子もいました。
じゃがいもも大きなじゃがいもが出るわ!出るわ!の大収穫となりました。育ててくれた藤岡さんや田中さんに「いっぱい掘れたよ~!」「ありがと~!」とお礼を行って帰りました。どうやって食べるのかも楽しみです。
〈プレ年少〉
たんぽぽ組は今年畑の土の状態と衛生面のことを考えてじゃがいも掘りを中止としました。そのかわり「駐車場に植えてある玉ねぎを抜いたらいいわ!!」と園長に案をもらい子ども達で協力して玉ねぎを抜きました。玉ねぎが抜けた瞬間「ペタン」と尻もちつく子、「とれた〜!」と笑顔いっぱい言う子等色んな姿が見られて教師も自然と笑みがでました。次の給食のカレーライスには子ども達が植えて収穫したじゃがいもと玉ねぎたっぷり入っていることでしょう。楽しみです!!
コメント (「じゃがいも掘りがありました」 らいおん組今岡美奈穂 はコメントを受け付けていません)










































































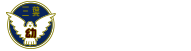

コメント (卒園2日前の年長の子ども達♪ はコメントを受け付けていません)