- blog
- album
- (089)-952-1777
- mituba@mituba.net
幼稚園の日記(ブログ)
2023年4月29日 土曜日
新年度が始まって1ヶ月がたとうとしています。令和5年度のみかん組は新入園児10名ともも組から進級した6名でスタートしました。最初の頃は新入園児が泣くのはもちろんのこと、もも組からきた子どもが雰囲気が違うことを敏感に感じ取って、元の保育室や保育教諭が恋しくなって泣き始めると、他の子にも広がって一斉に泣き始め大さわぎ!という日もありました。しかし少しずつ保育教諭にも馴染み、回りを見回しては気になる玩具を触ったり、テラスと保育室を出たり入ったりしながら、行動範囲もどんどん広がっていきました。日に日にできることも増えていき、朝登園してくると、保育教諭と一緒にかばんの中から持ち物を出して、決められた場所に片付けようとしたり、自分のマークも少しずつ覚えて手拭きタオル掛けようとしたりするようになりました。手拭きタオルのひもを両手で広げてちょっと背伸びしながらいっしょうけんめいフックにかけようとする姿を見ながら「がんばれ!」「もうちょっと!」とみんなで応援しています。これはちょっと難しいかな?分からないかな?と思うこともすぐにできるようになっていたり、理解し行動しようとしたりと、この時期の子ども達の発達と吸収力の速さには驚かされます。
今、園庭は工事中ということで狭くなっていますが、幼稚園児たちの様子を見つつ、合間を狙ってできるだけ園庭に出るようにしています。砂場の奥のスマイルハウスの回りが今のみかん組のお気に入りの場所です。保育教諭と一緒にスコップやボウル、コップなどを運んでいき、思い思いに遊び始めます。新入園児のFちゃんはまだ泣くことも多く、外遊びにも興味を示さないので、この日も保育教諭に抱かれたまま周りの様子を見ていました。すると急に砂に手を伸ばして触り始めたのです。手のひらについた砂を『なんだこれ?』とちょっぴり不快そうに砂をはらうように手を振ってみたり、ズボンにこすりつけてみたり、初めての砂の感触を確かめているようでした。そのうち自分で地面に座り、珍しそうに側にあったスコップを持ってみて、置くと、今度は大きなお鍋を持ち上げようとしたり、積極的に目につく周りにある物の感触を確かめたり試したりして遊ぶ姿が見られるようになりました。時々思い出しては泣きそうになりますが、側に保育教諭がいることが分かると、安心したようにまた遊び始め、更に小石や木の枝にも気付いてじっと見つめては投げるなど、身近な発見に夢中になっていました。
慣れてくると室内でもいろいろな遊びに興味を持って関わるようになってきました。まだ始まったばかりのみかん組の子ども達がどんな遊びが好きなのか、どんなことに興味を示すのか私たち保育教諭も知りたいと思い、クレヨン、シール、ボール、紙、粘土などいろいろな遊びを同時に出してみました。クレヨンは紙だけでなく、机や床にまで描く子もいました。シールも思いのままにペッタンペッタン貼っていき、服にまでくっついていました。粘土も口に入れる子もいなくて感心しました。いろいろな遊びの中でたくさんの気付きがありました。その中でも紙をちぎって遊ぶのは大人気で、紙に触ると振り回してみたり、左右に思い切り引っ張って破ろうとしたり、切れ目のところに指をかけてビリビリといい音を楽しんだり、思い思いに紙の感触を楽しんでいました。
まだ始まったばかりのみかん組の子ども達の成長が今からとっても楽しみです。毎日笑顔で『おはよう!』をし、笑顔で『バイバイ、また明日!』ができるよう、子どもたちにとってより良い保育をしていこうと思います。
2023年3月3日 金曜日
3月3日、今日はひなまつり。今年はただのひな祭りではありません。12月に延期されていたもちつきもあったのです。
実は、ひな祭りもちつきは朝からではなく、昨日の放課後から始まっていたのです!!
昨日の放課後、もちつきのために教師たちは、「ああかな、こうかな」とお土産用のひしもちを試行錯誤しながら作っていました。つきたてのおもちを1うす分もろぶたに伸ばして広げ、固まったところで、古森先生がひし形に切っていきました。そしてそこには、少しの切れはしのおもちがでていたのです。そのおもちに目を光らせていたのは、2Fテラスから応援していた年長さんです。古森先生の「見られちゃったかしら。ここは食べてもいいんだけど..」の一言も聞き逃しません。さっきまで2Fテラスにいたはずなのに、気付けばもう目の前にいるではありませんか。「おもち下さい♪」とニコニコでお願いされるとあげないわけにはいきません。「おいし~!!」の声を聞きつけ、次々に年長さんがやってきました。すると「お金あったら買えますか?」と聞く子、両手を合わせ「ありがとうございます。」と拝むように感謝する子、今日来れないことが分かっていたHちゃんは「ひみつよ」と大きめのおもちをもらうと、まるでまっくろくろすけをつかまえるかのようにパチンッと手でかくしうれしそうに持って帰るなど、前日から可愛いエピソードで盛りだくさんでした。
そして、楽しみいっぱいで迎えた当日。今日も朝から教師たちがせっせと準備する様子を2Fテラスから「〇〇先生がんばれー!〇〇先もがんばれ!!」とアイドルになったのかと思ってしまうほど、子どもたちの応援の声が聞こえていました。
すると…もち米をむしている釜の横で古森先生、N先生が何やらいいことをしているではありませんか!!年長さんは急いでかけつけます。なんと、そこではわりばしにおもちをさして、〝焼きもち‘’をしていたのです。炭であっためられたもちは、プク~とふくらみます。そのおもちは先生たちの口の中へパクッと入ります。それを見た子どもたちは「ズルーイ!」とほっぺをふくらまして怒っています。すると、くまぐみのEちゃんの口にもポイッともちが入ってきました。その瞬間、Eちゃんは口を押さえ「どうしよ、おいしすぎる、どうしよ」とニヤニヤやが止まりません。そして、何人もの子たちが実際に焼くことまで経験することができました。
そして、笑ってしまったのは、まるでご飯を作っているお母さんの横をちょこちょこして味見させて~と言わんばかりの勢いで、古森先生に「あんこ食べたーい」とお願いしたり、うすくもちをめん棒で伸ばしているのを見て「顔のマッサージみたい!うちのママもしてる(笑)」と世間話をして笑ったり、無邪気な可愛いさをたくさん見せてくれました。
自分たちでおもちをついた後には、あんころもちを食べられることを知り、子どもたらは大喜び♪「おもちはのどにつまったらダメだから、しっかりかみきること」を約束すると、あんころもちをビョーンとのばしながら食べたり、口のまわりにあんこをつけて泥棒のようになっていたり、あまりにも幸せそうに食べる子どもたちの表情を見て、教師たちも口元がゆるみっぱなしでした。
昼食後には、お待ちかねのお土産の準備です。自分たちの空っぽの弁当の中には、3色のひし形が配られました。実はひしもちの色には意味があるのです。教師にその意味を教えてもらうと「春を待ってる草はみどりだから1段目。冬は雪がふって寒かったね。だから2段目。今日はひな祭りで最後はももの花のピンクだね」とお話を読むかのように話しながら、ひしもちを完成させていました。
今日は子どもたちが本当のおだいりさまとおひなさまのように輝いていたひな祭りもちつきになりました。お家でもたくさんお話をぜひ聞いてみてください♪
コメント (「今日はうれしいひな祭り♪」 くま組 高松由衣 はコメントを受け付けていません)
2022年12月5日 月曜日
いよいよ今日は、今まで年長さんたちが自分たちで材料から集め、商品づくりや店内設置まで一生懸命してきたお店屋さんのみせじまいせーるです。先週、子どもたちが手書きの案内を家に持って帰って招待していました。
朝から園庭では「お店どうする?」と寒さ対策をしっかりとした厚着の教師たちが話し合っていました。そこへ園長が「寒くないのはあなたたちだけよ。子どもたちの服装見てごらん。身体をいっぱいいっぱい動かして遊ぶ服装でしょ?外であの服装で立っていたら凍えるよ。ねぇ、年長さん!」と朝早く登園してきた年長さんたちに声をかけました。するとブルブルしながら年長さんが「寒くなっちゃうから、ホール貸してください!」と本日の会場も決まりました。そこから大慌てで登園している年長を中心に準備が始まりました。
気付けばあっという間に10時前。お店の階段前にはもうお客さんが待っています。しかし…店内は商品や材料でぐっちゃぐちゃ。そこへ、商店街のオーナー園長がやってきました。「お客さんもう来てるよ!誰がやるの?」と聞かれ、「自分たちでやる!!!」と子どもたちに火がつきます。
*10時いよいよみせじまいせーる すたーと*
以前、年中、年少、プレの友達が買い物に来た時は、注文していないものをたくさん渡してしまったり、困っているお客さんを見逃してしまったりとなかなか大変な接客姿でした。
しかし、今日は誰が決めたわけでもなく、「私はこの役割!」という強い思いをもって働き始めたのです!!
お母さん、お父さん、おじいちゃん、おばあちゃんが門をくぐってやってくると「こちらですよ〜♪」とササっと上靴で園庭から案内する子(本当はいけません。いけない教師のマネをしています(笑))、階段のところで「いらっしゃいませ。お名前は書きましたか?こちらへどうぞ〜」と手を引く子、お客さんに「何が買いたいですか?この〇〇どうですか?」と声をかける子、教師に駆け寄り「おもちゃの鉄砲売ったらね、お客さんが“ありがとう“って言ってくれるんよ。うれしいね♡」と幸せそうに話す子、「お気をつけてお帰りください。ありがとうございました‼︎」と丁寧にお辞儀をする子、お店屋さんのやりとりの中で、人とかかわることで子どもたちの心は育っていきます。
保護者のみなさま、子どもたちからの招待状を信じてくださったり、メールを子どもたちに読ませてくださったりとたくさん協力していただいてありがとうございました。仕事の都合をつけてくださった方、家からお金を作ってきてくれた方、お店に来られなくてもお家でたくさん話を聞いてくださった方、商品を宣伝をするために可愛く子どもたちを変身させてくださった方、子どもたちのお店屋さんができたのも保護者の協力があってこそです。今日のお店屋さんもバザー・運動会どの行事も園と保護者の皆様が両輪になって子どもたちを支えていける環境であることに感謝です。ありがとうございました。
今日もご家庭で子どもたちの楽しい話をめい一杯聞いてあげてください♪
コメント (「みせじまいせーる!!」 くま組 髙松由衣 はコメントを受け付けていません)
2022年7月20日 水曜日
昨日の雨が大雨が嘘だったのかと思う程の晴天の中、1学期の最終日を迎えました。
進級・入園して約3か月。今年度の三葉っ子たちは、コロナ禍の中で大人に負けないくらいの知恵や行動力を遊びや毎日の生活の中で身につけてきました。言われなくてもさり気なく置かれた横断歩道の横の旗を見つけると手にして、高く上げ左右を確かめて渡ったり、ピタゴラ水遊びで「ああでもない、こうでもない。」とせっせと役割を分担したり、話し合って調節したり、どこを見ても「三葉っこってすごいな!」と感心させられるばかりです。
さて、今朝は太陽が照って真夏を思わせる空の下、子どもたちが登園すると、R4年度終園式が始まります。昨日の予定では、コロナ対策として園庭での終園式を計画していましたが、この炎天下では熱中症の心配もあるということで、急遽、会議室に変更し集合です。鼻までしっかりマスクをつけると、目がきりっと変わりかっこいい年長さんになり、背筋をしっかりと伸ばして会議室へ向かいます。
コロナ禍の中で自分の身を守るすべを身に付けてきた子どもたちは、大きな声を出さなくても習いたての手話を使って気持ちを伝えることができるのです。「おはようございます。」「おめでとう♪」「はーい。」どれも小さい声と手話の身振り手振りで挨拶も誕生日の友達へのお祝いの言葉も、そして、お話をしっかりと聞いて「うんうん。」とうなずいたり、どんなに距離が離れていても話をよく理解し、頭の中でイメージができるのです。古森先生から気を付けないといけないことなど、夏休み中のお約束を話してもらいました。子どもたちは、気を付けないといけないことがたくさんあります!!「熱中症に…コロナに…台風!もういっぱい頭使わんと!」と指を折りながら少し慌てるAくん、「よし‼これでコロナは入ってこないぞ♪」とマスクを鼻まであげ、満足そうな笑顔を見せるMちゃん、話を聞いてそれぞれ違った思いを話す姿に大人みたいだなと思わずクスッと笑ってしまいました。
そして、15分ほどの終園式を終えて帰り、「夏休みの約束なんやったけ?」と尋ねてみると…「アイスくれそうでも知らん人についていったらだめなんよ!」「ピンポーンって鳴っても出たらだめ。1人ででかけるのもいかんよ!」「マスクも鼻までしっかりしてね。」と右左右とやって見せてくれました。まるで小さな古森先生がたくさんいるようで、本当に理解力やイメージする力が備わった子どもたちに「さすが‼」と思うばかりの1学期の最後の日でした。
そして、1学期毎日過ごした保育室も子どもたちと一緒に掃除をしました。「ここ、ホコリたまっとる!」「あそこはまだキレイになりそう。」と子どもたちのお掃除センサーはピカイチです。お部屋も心もキレイに整理して今学期最後の1日を終えることができました。年長児は預かり保育の園児以外は8月のお泊り保育の日に、みんなが揃います。その日がとっても楽しみです♪
本日の引き渡し訓練では、ご協力ありがとうございました。現実、災害がないことを祈るばかりですが、万一に備えての準備は必要です。幼い子ども達を預かる者として、どんなに頑張っても私たちの力は微々たるものです。保護者の皆様のご協力により、教職員と保護者が両輪となって、子ども達を守っていきたいと思います。
今後とも保育現場でのご協力をお願いすることがあると思います。よろしくお願いいたします。
コメント (「1学期 終園式」 くま組 髙松由衣 はコメントを受け付けていません)
2022年6月8日 水曜日
今日は、全日実習でくま組、うさぎ組で廃材を使っての制作をしました。昨日、実習生がその計画を降園前に話をしてくれていたため、クラスの子達が「廃材持ってきたよ~」と元気良く登園してきました。楽しみにしていた子も多く、「こんなの作ろうかなって持ってきた!」と嬉しそうに見せてくれました。
うさぎ組では、実習生が絵本を読んでくれて、服やカバン、帽子、時計など自分が身に付けたい物を作ってオシャレをしようと声を掛けて廃材や紙袋、ナイロン袋を使ってイメージした物を作っていきました。Iちゃんは、赤色チェックのナイロン袋の下をハサミで切って、手提げの部分を肩にかけて洋服を作りました。それだけでは足りず、クレヨンでリボンを描いて可愛く工夫したりとまるでデザイナーのような姿が見られ、とても可愛いなと思いました。O君は、「時計を作りたい!」と大はりきり。自分の腕に合うようにチラシを何回も巻き直してサイズを合わせたり、針が無いからと厚紙を切って3時に合わせて貼ったりしていました。「なんで3時なの?」と聞くと、「3時が好きだから!おやつが食べられるから!」と嬉しそうに答えていました。同じ廃材であっても、その子その子のイメージがあり、そこから何が生まれてくるのか予測もつきません。子どもは教師が思っている以上に多面的な発想を持っていて、制作している子を見ていると驚かされます。型にはまったものではなく、1人1人が自由に作れるというのは子どもも教師も楽しめることなんだと改めて感じました。
くま組では、色々な動物、生物、虫を制作していました。最初は、個人で1つずつ作っていましたが、自分が作った動物の住む所を作ったり、ダンボールをちぎって看板を作ったり、柵を作ったりと周りにある物まで作り始めました。それを見た子ども達は、「私も作る!」と協力して作っていきました。目に見えるように作った物を飾ることで「あっこれが足りない!◯◯ちゃん手伝って!」と共同作品になっていきました。
年中児、年長児、それぞれ月齢は違いますが、その年齢に応じた援助をすることで、自分のイメージした物を作って達成感を感じられるんだと思いました。子ども同士、お互いが刺激し合いながら共に育ち合う姿を楽しんで見ていきたいと思いました。
今日は、昨日年長児が生石農園へ行って収穫してくれたビワをお土産で持って帰っています。三葉の農園で育ち、実った甘くて美味しいビワです。家族みんなで食べてみてください。
コメント (『これどうかな?』 うさぎ組 岸田亜寿美 はコメントを受け付けていません)
2022年2月2日 水曜日
昨日、屋外ステージで始まった発表会の自主練習は今日も盛り上がっていました。ぱんだ組のKくんは登園して所持品の始末を終えると、いそいそとぞうりに履き替えて「いってきまーす!」とステージへ飛び出していきました。時刻はまだ8時過ぎで、欲張りじいさん役はKくん一人でしたがそんなことは気にせず、小さな体を目一杯動かして堂々と欲張りじいさんを演じていました。
私が驚かされたのは、Kくんだけではありません。ステージで練習する子ども達が徐々に増えてきた頃、ふとステージに目をやると年中4クラスの子ども達が入り交じって練習していたのです。普段は赤と青の2コースに分かれて練習していますが、コースの枠を超えて子ども達が自分で考えて参加し、臆することなく自然と言葉を交わしながら練習していて、これがまさに三葉っ子の姿だなと昨年受け持っていた子ども達の成長を嬉しく思いました。
又、今日は発表会の座席のくじ引きも行いました。換気や密集、密接に注意しながら座席のくじを引いて、発表会の日にお父さんやお母さんに来てもらうことを楽しみにしていました。しかし、コロナ感染症・オミクロン株の感染拡大が続くなか、三葉幼稚園でも家族内感染による濃厚接触者がここ3週間を中心に発生し、松山市の指導により必要と判断された場合にはお知らせしているところです。今月に入って近辺の学校等の兄弟の感染により、濃厚接触者の連絡が入っています。その為、生活発表会の開催においても発表会前日に感染者が出た場合は、中止にせざるを得ない状況です。只今、屋外ステージを使ってどうにか開催できないものかと教師達で話し合っているところですので、日程等決まりましたらお知らせします。その時はご協力をお願いします。
屋外ステージの隣では、いよかんを使ったままごとが盛り上がっていました。このいよかんは、先日屋外遊ぎ場の果樹園で収穫したもので、小さかったり少し痛んだりしたものをままごとで使っています。ひつじ組のIくんは、いよかんを2つに切って絞り器で絞ると、「先生!いいにおいがするよ!」と笑顔でコップを差し出してくれました。いよかんの爽やかな酸味の香りは、果汁100%の本物のジュースです。本物の野菜や果物を本物の包丁や調理器具で料理する三葉幼稚園のままごとは、今日も活気に溢れていました。
明日、2月3日は節分です。年長児は身の回りにある廃材を使って鬼のお面を作りました。お面作りはお茶の子さいさいの子ども達。新聞紙を折ると頭に合うサイズに調整してセロハンテープで留めました。そこに付けるお面が、それぞれ違って面白いのが三葉っ子達です。箱に穴を開けて覗けるように工夫し被れるお面を作る子や髪の毛やひげを毛糸を使ってリアルに表現する子など、それぞれに工夫の凝らしたお面ができあがりました。明日は恵方巻の節分給食ということで、登園を楽しみにしている子ども達でした。
コメント (「三葉っ子らしさがいっぱい♪」 くま組 丸山利夫 はコメントを受け付けていません)
2022年1月11日 火曜日
今日から3学期が始まりました。冬休み明けに子ども達と楽しもうと準備していた凧作りやこま回しなどは生憎の雨でできませんでしたが、晴れた日には戸外で思いっきりお正月遊びもしたいと思います。
久しぶりの登園だった子も元気よく「おはようございます」「あけましておめでとうございます」と挨拶をして元気いっぱいの笑顔で門を入ってきました。明日から2歳児クラス(たんぽぽ黄組)が新しく始まるにあたって保育室の配置を少し変更したため、子ども達が迷わないようにと教師達がクラスの表示を大きく作って見やすい場所に貼って誘導します。それに気が付いた子ども達は、「あったよー!」と指差して駆け寄ったり、迷っている年少児を年長児が連れて行ってあげたりしていました。明日からプレ年少児よりも小さいお友達が来ることを心待ちにしている子ども達です。
年明けから右肩上がりに増えているコロナウイルスの感染症ですが、新種のオミクロン株は感染力が強いため、密を回避することや換気、手指の消毒には今まで以上に気を付けなければなりません。今日もテラスや大型テントの下を使って密にならないように遊んだり、向かい合ったり頭を寄せ合ったりして遊ばないような環境を作ったり工夫しています。感染症に気を付けながらも子ども達が安全に、そして楽しく遊べるような保育をしていきたいと思います。
これからも検温、マスク着用、手指の消毒は今まで以上にご協力ください。
さて、始園式は蜜を避けるため、各保育室で園内放送で行いました。園長からは、新しいコロナは子ども達が大好きでうつりやすいこと。うつらないためにも大声ではしゃいだりマスクを着けずに歌ったりしなようにしながら発表会に向けて頑張ることを話してもらいました。3学期は1つ上の学年になるための準備の学期です。それぞれの学年で目標をもち、締めくくりの学期にしたいと思います。
ここで、嬉しいエピソードの紹介です。1月8日土曜日の愛媛新聞「読者の広場」に久万高原町の方がアベノマスクを再利用することは賢い方法だという投稿をしてくださっていました。こうした励ましを力にして3学期も頑張っていきたいと思います。
愛媛新聞 1月8日土曜日 ━こだま 読者の広場━ より
「アベノマスク再利用は賢明」
投稿してくださった小倉様 ありがとうございました。
コメント (「3学期が始まったよ!」 くま組 丸山利夫 はコメントを受け付けていません)



















































































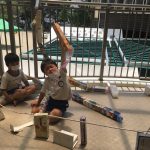





















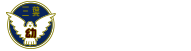

コメント (「泣いて、笑って、いっぱい遊んだよ!」 ひよこ みかん組 山岡由紀子 はコメントを受け付けていません)