令和6年度 幼稚園自己評価結果
園の教職員の自己評価に合わせて、保護者の皆様にも評価を頂き、今年度の園運営や教育活動の総括と来年度の改善に向けての課題等をまとめました。
1.園の教育方針(園経営、学級経営)
| 課題別自己評価 |
園関係者の評価と課題 |
☆本園の保育の目標とする幼児の姿
(1) みんなと仲良く(仲間)
(2) 健康な心と体(笑顔、元気、やる気)
(3) 自分で考えてやり抜く(自主性)
(4) 素直に感じ、表現する(心~創造性) |
コロナ禍以降継続してきた「子どもだけの行事」は、働く保護者の負担軽減や子どもの自主性、協調性の育ちにつながっている。又、子どもは知恵と工夫、助け合い、やり遂げた満足感や自信を培うことができ、本園の目標とする主体的に活動する姿が見られた。保護者には、こうした子どもの育ちを感じ取ってもらうことができ、労いの言葉を多く頂いた。来年度の行事については、働いている家庭が多いことや諸事情により行事を欠席せざるを得ない保護者や子どもがいるという現状にも考慮しながら、子どもの生き生きとした普段と変わらない姿を見てもらえるように内容について検討していきたい。
|
☆令和6年度の指導の重点目標 次の4点です。
1.自分から環境に関わって遊ぼう
2.健康で安全な生活の仕方を身に付ける
3.自分のことは自分でしよう
4.自分達で出来ることは協力してやり遂げよう |
1.教育課程の編成と取り組み
| 取り組み状況 |
反省・評価・改善 |
既に作成している教育課程、指導計画を毎期見直し、反省評価し、状況に応じて変更を重ねてきた。
今年度は新しい園舎での行事の実施の見直しや環境構成等、状況に合わせて保育計画を柔軟に変更し、重点目標の達成に向けて力を注いできた。
|
新園舎完成後、新しい保育施設での三葉祭り、秋の運動会、作品展等の行事の開催となったが、行事を通して子どもの主体性や創造性、協調性の育ちや家庭では見られない表情を見てもらうことができた。新園舎では年長、年中児が2クラス合同の保育形態をとることができるようになり、今まで以上に子どもの活動や教師とのかかわりの自由性が広がった。来年度も自由に主体的に活動ができる環境構成や教師の援助を大切にしながら、本園が理想とする遊びから学び、子ども中心の保育に努めていきたい。 |
2.保育の計画性
| 取り組み状況 |
反省・評価・改善 |
昨年度の教育課程と実践結果を見直し、学年縦割りで連携しながら、園全体で子どもの興味に合わせて柔軟に保育を行ってきた。
今年度は2クラス合同の保育運営を検討し、昨年度の反省や評価も含めて保育計画を見直し、四季折々の行事やその時しか体験できないことを取り入れ実践することで、多くの体験をすることができた。
|
環境による遊びを中心にした教育は、子どもが満足できるまでやり遂げる時間や空間、教師の子どもへの信頼が必要である。又、子どもの活動をより具体的にイメージし、次につながる環境を考えて、遊びの場を提供することが大切である。今年度は従来の保育活動の内容を検討し直し「楽しいことを思い出す会」等の新しい活動に取り組むことで、子どもの期待感や満足感が増すと共に子どもと教師が思いを共有したり、共に楽しんだりする機会が増え、子どもと教師との信頼が深まった。 |
3.保育の在り方 (幼児への対応)
| 取り組み状況 |
反省・評価・改善 |
幼児期は発達差が大きく一律ではない。中には特別に支援の必要な幼児も生活しており、一人ひとりの個性に寄り添った保育をしていく必要がある。そのため、全教師が連携を取り合い、視野を広げ、日々報告、反省評価し、一人ひとりの育ちや課題を確かめ、翌日の保育に活かしている。
クラス差や教師の経験の差に対しては、経験豊富な教師と一緒に指導に当たる等、連携を密にしながら質の高い保育に努めてきた。
|
特別に支援が必要な幼児に対しては、園長を始め、園内の特別支援コーディネーターを中心として支援について話し合い、全教師で連携を取り合いながらかかわることで、お互いを認め合い、共に成長する姿につながった。環境作りや幼児へのかかわりは、教師の感性や判断、気づきと創意工夫、実行力が必要である。今年度は怪我につながる事案が数件あった為、日々のヒヤリハットを検証し、保育活動、遊具の使い方、教師の配置等について話し合い、再発防止に努めていきたい。又、熱性けいれんやアレルギーなどの既往歴の把握、看護師との連携を密にし、発症時の処置や対応を徹底していきたい。合同保育やチーム保育をする中で、教師がお互いの保育を見合いながら、より良い保育の在り方や幼児への対応について考え、特に幼児に対する言葉遣いや態度に留意し、信頼関係を築くことができた。 |
4.保育の在り方(3歳未満児への対応)
| 取り組み状況 |
反省・評価・改善 |
幼稚園と保育園の両方の機能を併せ持つ施設として、幼保一貫教育に努め、食事や排泄等の生活習慣の定着に向けて、個々の発達段階に合わせた養護を心掛け、援助してきた。2歳児の幼稚園への移行については、スムーズな移行に向けて幼稚園と保育園との間での連携を密にしてきた。又、幼稚園児と保育園児が自然にかかわりをもてるように園庭の共有や行事にも参加できるようにした。
|
3歳未満児への対応としては、概ね月齢や個人に合わせたかかわりや配慮、遊びの環境作りをすることができた。1・2歳児は毎日の連絡ノートの交換で家庭からの健康状態や連絡事項を把握し、その日の出来事等をできる限り保護者に報告することができるよう努めてきた。環境作りについては、未満児の行動を予測し、危険防止に留意しながら異年齢児と触れ合う機会がもてるように計画してきた。食事中の誤嚥や午睡中の窒息等、未満児の特性を十分に理解し、事故防止に努めていく。
|
5.保護者への対応
| 取り組み状況 |
反省・評価・改善 |
今年度は保護者総会、参観日、各行事を通して子どもの園での活動の様子を見てもらい、個別懇談でコミュニケーションを図ってきた。又、「こどもだけの」行事は継続してほしいという意見が多かったため、今年度も実施し、保護者が見ることのできない部分については、ブログやインスタグラムを通して見てもらえるように対応した。保護者アンケートからは、ドライブスルーでの送迎により、教師との会話の機会が減ったことから保護者とのコミュニケーションが不足の傾向にあることが分かった。 |
働いている家庭が約8割を占める現状も考慮しながら、保護者に普段の子どもの様子を見ていただけるように行事等を計画し、実施してきた。昨年度の保護者アンケートから継続してほしいと要望の多かった「こどもだけ」の行事については、今年度も好評で感謝の言葉をたくさんいただき、教師の励みとなった。保護者からの苦情や相談については、園全体で解決策や今後の方針について協議し問題解決に努めてきたが、保護者との信頼関係の構築やいかにコミュニケーションを図っていくかといった点を課題としたい。 |
6.保育教員としての資質
| 取り組み状況 |
反省・評価・改善 |
保育教員、職員が連携を取り合い、幼児一人ひとりに合った援助や配慮を必要に応じて行えるように心掛けている。又、保育の質は環境づくりと働く保育教諭の人となりで決まることから、日々の職員会で保育の反省、評価をできる限り行い、より良い保育ができる組織作りに努めている。又、できるだけ研修に参加し、保育の知識や実践力を身に付けられるように研鑽している。 |
2クラス合同保育やチーム保育といった本園の保育形態を活かし、教員同士で保育を見合い、振り返り、保育の質や保育教員としての資質の向上に努めてきた。クラスの問題を担任だけが抱え込むのではなく、多数の教師の目で確かめ、話し合った上で判断し、適切な保育や援助ができるようにしてきた。又、保育経験によるクラス格差は、様々な教員が多方面から指導助言することで、教員の個性を伸ばし、組織としての総合力で補ってきた。保育の質を高めていくために今後も様々な研修会や学習会に参加し、保育の実践力を高めていきたい。 |
7.地域とのかかわり、地域子育て支援
| 取り組み状況 |
反省・評価・改善 |
|
下記の地域交流活動
○三葉祭り(卒園児、地域の方を招待)
○秋祭りの獅子舞、神輿出張披露(山西町仁喜多津会)
○ミキスタディ交流、英語教室交流(年長・年中児)
○田植え・稲刈り、さつまいもの栽培収穫(レインボーファーム)
○松山市移動図書館(中央図書館出張)の利用(年長児)
○味生第二小学校社会科見学(北斎院町秀野邸)
○宮前小学校2年生遠足(さんさんらんど)
【その他】一時預かり保育(ぴよぴよ)、病児病後児保育(三葉病児園)、学童保育、教育相談、園庭・プール開放等、地域の子育て支援活動を行っている。
|
昨年度の保護者アンケートの回答から継続して行ってほしいとの意見が多かった「子どもだけの」行事については今年度も継続して行った。新園舎お披露目を兼ねた三葉祭りには卒園児や地域の方々を招待し、盛大に開催し喜ばれた。
幼稚園が所有する秀野邸やさんさんらんどを開放し、味生第二小学校の社会科見学や宮前小学校2年生の遠足など地域に有益な施設の利用ができた。
昨年3月に開所した病児病後児保育「三葉病児園」は開所1年目で約700名の利用があり、近隣のみならず郊外からの利用者もおり、中予地区の働く親を支援する役割を担う機関としての実績を残すことができた。
|
8.研修、研究
| 取り組み状況 |
反省・評価・改善 |
〇園内研修
今年度も外部から講師を招いての園内研修は叶わなかったが、日々の職員会の中で保育を振り返り、子どもの様子や情報の共有、遊びから学びへとつながる環境構成について話し合う時間を割き、園内研修を行ってきた。又、2クラス合同の保育を行うことで、お互いの保育を見合ったり振り返ったりし、協同性の高い保育の実践につながった。
〇園外一般研修
公的機関による研修、県、中予地区研修、学習会等、行事と重なっていない研修には参加することができた。リモート研修や対面式の研修、県外の研究大会に参加することで、他園の教諭と意見を交えながら保育について理解を深めることができた。
|
保育の質の向上には、日々の保育の振り返りや評価、改善と共に研修や学習会への参加も不可欠である。コロナ禍を機に開始されたリモートやオンデマンド配信の研修に参加することで、多種多様な内容を学習することができた。保育終了後の職員会は、教員間の意識統一や情報共有の場として大切な時間であり、保育や行事に向けて教員の同僚性やチーム保育の質を高めることにつながった。今後も他の業務との兼ね合いも考えながら、業務改善に向けての見直しや工夫をしていきたい。 「子どもだけ」の行事を今年度も継続して計画、実施したことで、幼児が主体的に活動する姿が見られ、幼児教育のやりがいを感じることができた。
|
★施設の利用
令和6年度は新園舎が完成したことで、2クラス合同の保育活動やチーム保育の活性化、雨天時の3階ホールでの保育園運動会の開催等、新しい園舎の機能を活かした保育運営をすることができた。特に今夏は熱中症警戒アラートが度々発令し、近隣の幼稚園や小学校では屋外でのプール遊びを止む無く中止することがあったが、本園の屋内プールでは熱中症を気にすることなく、9月中旬まで存分に水遊びを楽しむことができた。園舎建て替えにより第2園舎に移動していた図書を新園舎多目的室に戻したことで、子どもがより身近に教材として利用することができるようになった。屋外遊ぎ場「さんさんらんど」は、子どもが思いきり体を動かして遊ぶ場として、又、地域の小学生や他園との交流の場として利用することができた。併設する果樹園では、ブドウ、モモ、柿、伊予柑を収穫し、味わう体験をすることができた。屋外遊ぎ場の第2園舎は、1階を病児病後児保育、2階を一時預かり保育ぴよぴよとして利用し、みつばっこハウスは、従来通りの学童保育の施設として利用した。
◎会計面での監査は監査法人により既に終え、適切であるという評価を頂いております。
令和6年度学校評価 保護者アンケート結果報告
令和6年度学校評価アンケートにご協力いただきましてありがとうございました。幼稚園児373名中352名の方にご協力を得ることができました。この結果は、今後の園の運営に活かしていきたいと思います。アンケートの内容が自分のお子さんの育ちの面で評価になっているものがありましたが、この時期の子どもたちは発達や成長の仕方がそれぞれ違います。他の子との比較ではなく、日々のお子さんの成長を見つけ、見守り、励ましてください。
お子さんが園生活を楽しんでいる姿や好奇心、感動の心、集団生活に必要な態度の育ちについては9割の方からA~Bの評価を頂いております。問題点については少数ではありますが個人的な思いもお書き頂いておりますので、参考までに集約してお届けいたします。
| A |
237名 |
67% |
| B |
103名 |
30% |
| C |
12名 |
3% |
| D |
0名 |
0% |
| 無回答 |
0名 |
0% |
| 合 計 |
352名 |
100% |
| A |
242名 |
68% |
| B |
98名 |
28% |
| C |
11名 |
3% |
| D |
1名 |
1% |
| 無回答 |
0名 |
0% |
| 合 計 |
352名 |
100% |
③友達と一緒に遊んだり友達の遊びに刺激を受けたりして共に過ごす楽しさを味わっている
| A |
283名 |
80% |
| B |
63名 |
18% |
| C |
5名 |
1% |
| D |
0名 |
0% |
| 無回答 |
1名 |
1% |
| 合 計 |
352名 |
100% |
④遊びや集団生活に必要な決まりを知り、守ろうとする態度がそだってきている
| A |
248名 |
69% |
| B |
94名 |
27% |
| C |
9名 |
3% |
| D |
0名 |
0% |
| 無回答 |
1名 |
1% |
| 合 計 |
352名 |
100% |
⑤さまざまな物事に興味関心を示し、知的好奇心や思考力、感動する心等が育ってきている
| A |
280名 |
79% |
| B |
70名 |
20% |
| C |
2名 |
1% |
| D |
0名 |
0% |
| 無回答 |
0名 |
0% |
| 合 計 |
352名 |
100% |
⑥自ら遊びを作り出す楽しさを味わい、幼稚園生活を楽しんでいる
| A |
271名 |
77% |
| B |
74名 |
20% |
| C |
6名 |
2% |
| D |
1名 |
1% |
| 無回答 |
0名 |
0% |
| 合 計 |
352名 |
100% |
⑦遊びの楽しさや達成感を味わい、自信を持って行動できるようになってきている
| A |
258名 |
73% |
| B |
89名 |
25% |
| C |
4名 |
1% |
| D |
1名 |
1% |
| 無回答 |
0名 |
0% |
| 合 計 |
352名 |
100% |
⑧集団の中で一人一人の幼児が自己を発揮し、互いに力を活かし合いながら共に学び合う様子が見られる
| A |
241名 |
68% |
| B |
101名 |
28% |
| C |
9名 |
3% |
| D |
0名 |
0% |
| 無回答 |
1名 |
1% |
| 合 計 |
352名 |
100% |
| A |
256名 |
73% |
| B |
83名 |
23% |
| C |
13名 |
4% |
| D |
0名 |
0% |
| 無回答 |
0名 |
0% |
| 合 計 |
352名 |
100% |
⑩人への信頼感や思いやりの気持ち、自己抑制力が育ってきている
| A |
225名 |
64% |
| B |
117名 |
33% |
| C |
10名 |
3% |
| D |
0名 |
0% |
| 無回答 |
0名 |
0% |
| 合 計 |
352名 |
100% |
| A |
168名 |
48% |
| B |
143名 |
40% |
| C |
38名 |
11% |
| D |
3名 |
1% |
| 無回答 |
0名 |
0% |
| 合 計 |
352名 |
100% |
⑫しっかり体を動かして遊び、体色が向上し、たくましさが育ってきている
| A |
273名 |
78% |
| B |
74名 |
20% |
| C |
4名 |
1% |
| D |
1名 |
1% |
| 無回答 |
0名 |
0% |
| 合 計 |
352名 |
100% |
⑬生命を尊重する心や自然を大切にする気持ちが育つ取組みがされている
| A |
244名 |
70% |
| B |
95名 |
26% |
| C |
12名 |
3% |
| D |
1名 |
1% |
| 無回答 |
0名 |
0% |
| 合 計 |
352名 |
100% |
⑭幼稚園は一人一人の幼児の育ちを保護者に伝えている
| A |
213名 |
61% |
| B |
111名 |
31% |
| C |
27名 |
7% |
| D |
1名 |
1% |
| 無回答 |
0名 |
0% |
| 合 計 |
352名 |
100% |
⑮園は感染予防に努めつつ、園児達に最大限の体験をさせるよう努力し、保護者も理解できている
| A |
283名 |
81% |
| B |
64名 |
18% |
| C |
5名 |
1% |
| D |
0名 |
0% |
| 無回答 |
0名 |
0% |
| 合 計 |
352名 |
100% |
| A |
234名 |
66% |
| B |
98名 |
28% |
| C |
19名 |
5% |
| D |
1名 |
1% |
| 無回答 |
0名 |
0% |
| 合 計 |
352名 |
100% |
| A |
99名 |
28% |
| B |
172名 |
48% |
| C |
66名 |
19% |
| D |
14名 |
4% |
| 無回答 |
1名 |
1% |
| 合 計 |
352名 |
100% |
⑱後援会活動は縮小されているが、保護者は関心が高く協力的である
| A |
154名 |
43% |
| B |
167名 |
47% |
| C |
27名 |
8% |
| D |
3名 |
1% |
| 無回答 |
1名 |
1% |
| 合 計 |
376名 |
100% |
⑲幼稚園は教育目標や指導の重点についてわかりやすく伝えている
| A |
217名 |
61% |
| B |
115名 |
33% |
| C |
16名 |
5% |
| D |
4名 |
1% |
| 無回答 |
1名 |
0% |
| 合 計 |
352名 |
100% |
⑳教育方針や指導の重点は、幼児や家庭、地域の実態にあっている
| A |
252名 |
71% |
| B |
92名 |
26% |
| C |
6名 |
2% |
| D |
0名 |
0% |
| 無回答 |
2名 |
1% |
| 合 計 |
352名 |
100% |
新園舎完成後、新しい保育施設での三葉祭り、秋の運動会、作品展等の行事の開催となりましたが、こうした行事を通して子ども達の主体性や創造性、協調性の育ちや家庭では見られない表情を見ていただくことができ、現状での行事実施に満足しているというご意見を多くいただきました。その一方で、保護者参加型の行事を増やしてほしい、コロナ禍前のような参加人数に制限のない行事を実施してほしいといったご意見も少数ではありますがいただいております。又、後援会活動の縮小や保護者の交流機会の減少から、保護者同士の関係が希薄化の傾向にあることも感じ取ることができました。来年度の行事については、働いているご家庭が多いことや諸事情により行事を欠席せざるを得ない保護者や子どもがいるという現状にも考慮しながら、子ども達の生き生きとした普段と変わらない姿を見ていただけるように行事の内容について検討していきたいと思います。
コロナ禍以降継続してきた「子どもだけの行事」は、働く保護者の負担軽減や子ども達の自主性、協調性の育ちや成長につながっていると実感することができました。本園の特色である食育では、子ども達が季節の野菜を収穫し自ら調理したり、四季折々の行事食を味わったりする機会が多くありました。今後も行事以外での昔からの伝統に触れる機会や体験を大切にしていきたいと思います。
新園舎では年長、年中児は2クラス合同の保育形態をとることができるようになり、今まで以上に子ども達の活動や教師達とのかかわりの自由性が広がり、その様子を子どもとの日常の会話や行事等を通して保護者の皆様に感じ取ってもらえたのではないかと思います。自由に主体的に活動ができる環境構成や教師の援助を大切にしながら、本園が理想とする遊びから学び、子ども中心の保育の実施に向けて努めていきたいと思います。
★要望・提案について
◎隣接している山西団地には約300世帯の方が住まれています。今年度も山西団地自治会の方と定期的に情報交換を行いながら、子どもたちの安全や教育のために便宜を図っていただいてきました。来年度も各種行事の開催や園児の送迎等でご迷惑をおかけすることがあると思いますが、保護者の皆様には子どもたちのために何卒ご協力お願いします。引き続き、送迎時の団地駐車場への駐停車、通行禁止の道路への進入や徐行運転に十分注意し、子どもの安全面(シーベルトの着用等)にも配慮していただきながらドライブスルーでの送迎にご理解ご協力いただきますようお願い致します。
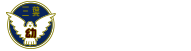

☆アンパンマン列車の遠足等の親子で参加できる行事をコロナ禍前のように開催してほしい。 ➡今年度もアンパンマン列車の親子遠足は計画しておりましたが、運営会社に問い合わせたところ列車の運行の都合で現在のところ予定がないとのことでした。親子参加の行事を増やしてほしいとの意見を少数いただいておりますが、8割以上の保護者が就労しており、参観日やお別れ会等の行事も欠席せざるを得ない方もいらっしゃいました。こうした現状にも配慮し、来年度の行事等の内容については検討していきたいと思います。
☆15:00代のお迎えの時間が制限されて困ることがあった。 ➡預かり保育のお迎えの時間が幾多に分かれることで、教師の対応や子どもの安全面での配慮が難しい状況が発生しており、時間を区切らせていただいております。今後もお迎え時間の集約にご協力お願い致します。
☆もう少し早めに行事の日時や内容を教えてほしい。 ➡申し訳ありません。年度初めにお渡しします年間行事予定に沿って行事等は実施していきますが、予測できない出来事や止むを得ず変更せざるを得ない状況もありますので、ご理解ください。
☆思い出写真館の写真が減り、園での子どもの様子がもう少し見られるようにしてほしい。 ➡教職員の業務見直しの一環として、今年度より実施して参りました。子ども達の園での様子は毎日のブログやインスタグラムの更新、毎月の思い出写真館を通して発信しておりますので、ご理解いただきたいと思います。
保護者の皆様のご理解ご協力、又、労いの言葉をたくさんいただき、教職員にとって何よりの力となっております。心より感謝申し上げます。ありがとうございました。教職員一同、これからも子どもを第一に考えて保育をしていきますのでよろしくお願い致します。