- blog
- album
- (089)-952-1777
- mituba@mituba.net
幼稚園の日記(ブログ)
2010年7月16日 金曜日
1学期が終了に近付き、室内の片付けをしたり、自分の持ち物の整理をしたりする中、昨日の見学会で沢山の来園者の方に見ていただいた作品展も片付けに入りました。子ども達の家族や友達に見てもらっただけでなく、来年入られる方々からも関心を寄せられ、1つ1つの作品をゆっくりとみて頂いたことを嬉しく思いました。こんなに素晴らしい作品をすぐに片付けてしまうことが惜しくてもっともっと沢山の人に見て頂きたいと今日まで大切に飾っていたのです。そこで今日は、揃ったクラスから自分の絵、自分の作品を大切にお部屋まで持ち帰りました。写真を撮っていると「ねえねえ、私の絵見てステキでしょう」とか「壊さんように持って降りんといかん」「お休みしている○○ちゃんのも持って降りんと」と言いながらせっせと手を動かしていました。作品を展示する時の嬉しそうな表情や言葉よりも子ども達の達成感を味わっている様子や一回り成長した頼もしい行動に驚きました。私達教師も子ども達の日々の成長の足を引っぱらないように人として先輩として最高の知恵をしぼっていきたいと思っています。
また、今日は今年度初めての地震避難訓練を行いました。実際は子ども達の訓練と同時に教師の訓練でもあります。時折震度1や2の揺れを感じただけでもヒヤっとするのに、南海地震のように大きなものが起こってしまった場合私達は命がけで子ども達の安全確保をしなければなりません。地震も火災も自然現象も訓練した時と同じ条件で起こるわけではありません。副園長の放送をよく聞いて状況を冷静に判断し次の指示が出るまで、机の下に隠れている子ども達は真剣そのものでした。家で地震が起こった時、どこかに外出していて起こった時、いろいろな所での安全な避難の仕方を教わりました。「地震の時はあせらないで、揺れがなくなったらあわてずに避難しましょう。今日は火災は起こっていません」という放送での指示は一人ひとりの教師が誘導の仕方を適切に判断し、子ども達の安全を確保するための手段を選びなさいという伝達でもありました。私達は緊張感を持ち、本当に起こった時に訓練が生かされなければと反省会では申し合わせました。子ども達も自分の命を守るための方法をその年齢なりに理解できるよう今後も、いろいろな経験を通して指導していきたいと思います。
家庭でも、もし地震が起こったらお家の中ならどこが安全なのか、もしも家族が別々の所に居る時に地震や災害に遭ったらどうするか話し合っておくことも大切なことです
今日は1学期最後の手作り給食でした。朝から楽しみにしていた子ども達は避難訓練の後、すぐに準備をして並んでいました。栄養満点の黒豆ごはんに豆乳シチュー、サツマイモの天ぷらにかぼちゃ煮、そしてこの夏はじめてのゴーヤのサラダは最高でした。
副園長が子ども達の体のことを考え、お母さん方のお手伝いを得て今日もおいしくいただきました。それから、きりん組の金本さんからシラスをいただきごはんと共にいただきました。ありがとうございました。
1学期もあと残すところ1日となりました。有意義な1日にしたいと思います。
2010年7月6日 火曜日
やっと出来ました!立派なやぐら。お祭りにはほとんど参加したことのない私ですが、このやぐらを見てうきうきしてきました。子どもたちもやぐらを見てお祭り気分になり、たくさん集まって来るのではないかな・・・!?と朝楽しみにしてバスに乗りました。バスから帰ってくると聞こえてきました!「ポーニョポーニョポニョさかなのこ♪」とても上手に歌っている声が聞こえ、気が付くと私も一緒に歌っていました。年少児から年長児まで、しっかりマイクを持ち歌う姿を見て、“かわいいな”と見とれてしまいました。また今日は夕涼み会で行われる各コーナーのポスターが園舎に貼られていました。そこにはたくさんのカラー帽子の観客が集まっていました。「カラオケあるんや。楽しそうだから行こう!」と言っているのを聞いて、大人のような会話だなと思いました。
今日の盆踊りでは、うちわを持って踊ってみました。大きな丸に青、黄、赤のうちわがとてもきれいでした。うちわを片手に上手に踊っていた子どもたちは、少しずつ夕涼み会が近づいているのを感じているようでした。たいこをすることになった年長児は登園するとすぐに練習をしていました。その隣で同じようにリズムをとりながら年少児のHちゃんは「ぼくもたいこをしたい!」と言っていました。そのリズムうちはなかなかのもので、2年後が楽しみだなと思いました。
今日は火曜日コースのこあら保育でした。プール遊びが楽しみで、登園するとそのまま海の家に直行する姿も見られました。プールに行くと、凄い水しぶきで「キャー!濡れた!」とお母さんの声が響いて、私も思わず笑ってしまいました。「さあそろそろ上がろうか。」とお母さんが言うと、「いや!」と次は泣き声が響きます。まだ2歳児だと思っていたけれど、こあら保育で好きな遊びを見つけて遊び、自分の思いをしっかり持っていることにとても感心しました。自由な時間が終わって3階のおへやに上がると、今日の手作り給食が用意されていました。今日は園児達の手作り給食の日で、こあら組さんにも味わってもらおうと副園長が準備してくれたのでした。「今日の給食は、にんじん、トマト、じゃがいも、きゅうり、そして切り干し大根が園でとれたものです。」と言うと「えーこんなに!?」「切り干し大根も!?」という声が色々なところがら聞こえてきました。切り干し大根は昨年11月に子ども達と大根を細かく切って乾かしておいたものなのです。いただきますをすると、すぐの食べ始めたこあらさん。さっきまで泣いていた子も、遊んでいた子も、とてもおいしそうに食べていました。「この納豆美味しいですね!何が入っているんですか?」と興味津々のお母さんも美味しそうに食べていました。今日は急だったので、食事の時間が短くて、食べ終わるとすぐに降園になってしまいましたが、バスでも手作り給食の話題になっていました。「本当ラッキーだった!」と嬉しそうに言っていたお母さんを見て私も嬉しい気持ちになりました。園に戻るとどの学年もほとんどおかわりが残っていませんでした。くま組の子どもたちと一緒に食べたのですが、やっぱりどれも美味しかったです。手作りの温かさやおいしさを感じる気持ちは子どもも大人も同じなんだなあと感じました。
本日の手作り給食のメニュー
・5分づき米のにんじんとちりめんごはん
・さんまの竜田揚げ
・きゅうりと玉ねぎ、キャベツのマヨネーズサラダ
・にんじんの天ぷら
・ふかしじゃがいも
・りんご、ちくわ、ねぎ、のり入り納豆
・とり胸とワカメ、玉ねぎ、ビーフン入りお吸い物
コメント (「ラッキー!手作り給食食べちゃった」 くま組竹田佳那子 はコメントを受け付けていません)
2010年6月21日 月曜日
今日から自由参観日・作品展が始まりました。初日の今日、年長組は松山総合公園に出かけました。
梅雨に入り、今週いっぱいはぐづついたお天気になると予想されていたので、内心ドキドキしていましたが、曇りの天気で雨も降らず沢山の保護者の方々の参加を得ることができました。
年長組の目標は、頂上の展望台まで登ることです。副園長の説明の中に「今日のお天気は、湿度が高く気温も高いので、熱中症になりやすい状況にあるから水分をとりましょう」という話がありました。その話の通りで太陽は出ていないのに少し歩いただけで汗が出るほどでした。片道10分間で頂上まで登り、自分達の家の方向を指さして「お家が見える」「あれが幼稚園かな?」等と会話が弾みました。また、あじさいが満開で、あじさいロードを通る時にはくま組のAちゃんは「あじさいのトンネルみたい」と笑顔であじさいを見上げていました。
頂上に着くと「うわーお城みたいな建物だね」「すごくきれいね」と口ぐちに感じたことを言い合っていました。その建物から東の方を見ると、松山城が見えます。松山城の高さと展望台の建物の高さは同じだということを副園長から教えてもらった子ども達は、1番に松山城を見ようと目指して上がりました。「本当に同じぐらいの所に見えるよ」「うわー本当にすごいね」と興奮して見ていると、松山の街が見渡せることにも気付きました。松山城は松山市の中央(真ん中)にあって、街を四方八方に見下ろす位置にあります。このような城の建て方は全国にも類がなく、大変珍しくもあり、そして素晴らしいものなのだそうです。また、所々にマンホールがありますが、そのマークが椿の花です。これは「住みよい街松山へようこそ」と書かれてあり、松山のシンボルマークを取り入れた心遣いが嬉しいと思いました。今日は私たちの住んでいる松山について沢山」知ることができた1日となりました。(ちなみに愛媛県のシンボルマークはみかんの花です)
11:30にさくらの丘に戻って早速教師達が作ったおにぎりの昼食です。この企画を副園長から提案され、自分達のクラスの子ども達や保護者の方たちに担任がにぎったおにぎりを食べてもらいたいと私達も大賛成したのでした。朝早く出勤し、副園長指導のもと大きなおにぎりと野菜(年中さん、年少さんのお楽しみの為にナイショ!!)をワクワクしながら作りました。他の学年の時も楽しみにしておいて下さいね。(内容・レシピ等は年少さんが終わってからにします)
今日は、年長児にとって良い体験学習になりました。沢山の保護者の皆さんの参加、ありがとうございました。
コメント (「松山のいいところ発見」 くま組 原田寿子 はコメントを受け付けていません)
2010年5月28日 金曜日
毎朝、トマトや朝顔に「おはよう」と声を掛けている年長組の子ども達は、今日もせっせと水やりをしながら「まだトマトにはならんのかな?」「まだ朝顔の芽が出てないよ」などと友達と楽しく会話を弾ませていました。トマトの黄色い花も各クラスのプランターにちらほら見られ始め、子ども達の関心も高まってきています。
そんな中、以前に自分達の不注意で折れてしまったトマトを育てている4人組のA・B・C・D君達の鉢のプレートが牛乳パックで作られていた為、毎日の水やりや雨のせいでくしゃくしゃになっていました。そのことに副園長が気付いて「ちょっといい物持ってきてあげるから」と言って木片を持って来てくれました。そして、「ここから下(約3程)は土の中に入るから、この上の部分に自分の名前を書いてね」とマジックを手渡されました。4人は一人ひとり書く範囲を考えながら丁寧に書いて、出来上がるとそのプレートを持って一目散に走って行き鉢に差し込み笑顔で眺めていました。クラスで育てているトマトの成長より少し劣っているけれど、一生懸命大きくなろうとしているこの4人組のトマトの生命力に期待が持たれます。
一方、今日の砂場では、ひつじ組の子ども達が大活躍でした。昨日より更に山や川、そして水を流すパイプの位置や形が高度になり、一人ひとりが自分の役割を考えて遊びを進めていました。その中で今日も色々な学びがありました。できあがった山から山に渡した樋に水を流す子ども達は、何度も何度も繰り返し順番に並んで水を入れて行くのですが、その中に白い帽子が一人。そうです、たんぽぽ組さんが大きな入れ物に水を入れてさり気なく列に加わろうとしていたのです。いつものH君なら我よ我よと突き進むであろうと予想されるのですが、今日はこの遊びの一員になっているのでした。1度目の入れ物は大きすぎて樋にうまく流せず下に水が落ちてしまいました。それに気付き2度目からは小さめのお椀に代えて運んでいました。又、この遊びを始めたひつじ組のT君は、自分が渡した樋を友達がはずしたことで、これはなぜ必要かということを納得するように実際にやってみせながら説明する姿が見られました。これも遊びが充実しているからだと思います。一人では成り立たないこの遊びの中で、課題を与えたり少しルールを高度にしたりして、子ども達の学ぶ力のハードルを高くしていきたいと思います。
年長組は屋外遊ぎ場へ2回目のお散歩に行きました。少しタイヤゲームをした後、お待ちかねの築山へ・・・登る・ころがる・ジャンプする等何人もの子ども達が重なり合いながら無心に遊び、とにかくはじけて遊ぶ子ども達の楽しそうな表情に私たちの心もはじけていきました。
らいおん組のケアフル訪問でもホットな出来事がありました。一生懸命元気をあげている子ども達の姿に感動したお年寄りの方から「みんな、微笑みながらお手々つないでくれてありがとう。一生懸命元気を出してくれているからみんなから元気をもらったよ」と言っていただきました。今日の子どもたちの申し合わせは、笑顔・元気・おふざけをしないことでした。まさにそのままの言葉を頂いたのです。手をつないで触れ合うゲームでは、一人のおじいちゃんに誰もパートナーがいないことに気付いたYちゃんが、右手は自分のパートナーのおばあちゃんの手をにぎり、左手は伸ばしてその一人ぼっちのおじいちゃんの手をにぎる優しい光景が見られたのです。この老人施設訪問での交流は、幼稚園ではできない学びをすることができることも実感しました。
コメント (「子どもたちの知恵くらべ」 くま組 原田寿子 はコメントを受け付けていません)
2010年4月30日 金曜日
今年度初めての参観日は、沢山の保護者の方に来園して頂き、普段の子ども達の生活の様子を見て頂くいい機会になりました。朝早くに子ども達と一緒に登園されたお父さんは、「うわ、こんな遊びしよるんか?」と包丁を使ったままごとコーナーに興味を持たれていました。又、たんぽぽ組のYちゃんのお父さんは、きりん組の男の子達に誘われて、かけっこに加わると、加減せずに走って下さり、まわりからも「頑張れ」という声援が聞かれました。
ちゅうりっぷ組のT君もお母さんと2人だけのかけっこを楽しんでいました。こんなふうに普段から自分のしたい遊びをみつけて十分に遊んでいる姿を見て頂くことが、この参観日の目的であり、子ども達の本来の姿を知って頂ける嬉しさも感じています。
それぞれの学年で、保育参観を進める中で、唯一全学年同じ内容の物を入れました。それは、カイワレ大根の種をまいて、栽培する活動です。昨年の親子運動会で母の日にちなんでカイワレ大根をプレゼントしましたが、まいた種が少なかったことと、クラスによっては、時間が足りず、小さかったことが反省でした。今年こそは…と教師達が副園長と相談して企画したのです。そこで、連休前にまいておきたいと考え、今日の参観日で、保護者の方々の手を借りて準備をすることにしました。
カイワレってどうやって育つか知ってますか?なんで暗くするんだろう?何日で食べれるのかな?等々、いろいろな質問が出たクラスもありました。カイワレの種って見たことありますか?八百屋さんで売っているカイワレを見ても、種から育てることは、考えたことがないと思います。
毎日の生活の中で自然から教えられていることが多い三葉っ子達、このカイワレ大根の栽培からも命の不思議や食に関心を持つことができることでしょう。連休明けにどれくらい芽がでているか楽しみにしながらそっと種をまきました。
メインの保育参観では、親子運動会に向けて親子フォークダンスを踊ったり、ゲームをしたりする活動だけでなく、親子で触れ合える手遊びや、歌なども取り入れました。特に年長組は、スキンシップをたっぷりとって、親に甘えるチャンスも作りました。
総会が始まる頃、年少さんのお部屋から「お母さん」と泣き叫ぶ声があちらこちらから聞こえてきました。それを見た副園長がちゅうりっぷ組のお部屋へ行き、「あのね、古森先生がお母さんと大事なお話をしてくるから、それまでにお帰りのお支度をして待っててね」と言うと泣いていた子たちが、笑顔になって、うなづいたそうです。子ども達に、しっかり分かるように伝えることで、安心して待つことができたのです。このように、子ども達の気持ちを大切にしていきたいです。
さあ、長い連休に入ります。楽しい思い出を作り6日に元気よくあえることを楽しみにしています。
コメント (「親子の触れ合いっていいものですね」 くま組 原田寿子 はコメントを受け付けていません)
2010年3月4日 木曜日
今日は、雨がぱらぱらと降っていたので子どもたちは、お部屋でアルバム整理をしたり、絵の表紙を作ったりして思い出をまとめていきました。10時頃になると、雨が止みそれに気がついた子どもたちは「外に行ける!」と言って嬉しそうに飛び出していきました。戸外では、ひよこ組から教師までがリレーをし園庭は大にぎわいでした。バトンが、さくら組さんからくじら組さんへ、教師から教師へ、そしてその活気のある姿を見て「がんばれぇ!」と応援する子どもたち、その姿は、とても活気にあふれていました。また、今日と明日三葉に研修に来ている帝京幼稚園の新任の先生が思いっきりリレーに加わって走っているのを見た子どもたちは「すごい速い!」と目をキラキラさせました。そして、めいめいが「一緒に走ろう!」と誘ったり「並ぶ時は、座るんよ」と教えてあげたりする姿も見られました。明日も、子どもたちと戸外で元気いっぱいに体を動かして遊んで行きたいと思います。
今日、くま組では最後の習字がありました。菅野先生に、自分の名前の書いてあるお手本をもらいそれを見て丁寧に一字一字書き、穴がつぶれると「もう一回書く!」と言って自分の名前を丁寧に書いている姿が見られました。そして、「一年間ありがとうございました」と挨拶をして「せんせぇ」「習字頑張るね♪」とニコニコしながら話していました。
また、年長全クラスで卒園式の練習をしました。練習を重ねて日に日に姿勢がよくなり、大きな声で言葉が言えるようになった子どもたち。私は、そんな子どもたちを見て、「かっこいいなぁでも、卒園するの寂しいな」と思いました。卒園まで幼稚園に来るのは、あと、10日です。その10日間の一日一日を大切にして子どもたちといっぱい思い出を作っていきたいと思います。
コメント (「卒園式まで残り10日!くま組 中矢麻衣」 はコメントを受け付けていません)
2010年2月9日 火曜日
発表会が終わって2日後の今日、登園してきた子どもたちは、「ビリーブの時、お父さん泣きよったんよ」「Mのお母さんも泣きよったけど、A君のお母さん、もっと泣きよった」などと嬉しそうに話してくれました。暖かくて心地よい戸外では、クラスの帽子の色があちらこちらで固まって集団で遊ぶ姿が見られました。ひまわり組では、泥団子作りが始まると「お店屋さんつくろう!」ということになり、みんなでいくつもせっせと作っていました。それを見た、らいおん組の子どもたちも、ひまわりさんに負けんように!と団子作りを始めました。先に作り始めたひまわり組さんの数で負けていた、らいおん組は質がいいものを作ろうとピカピカの泥団子を丁寧に作っていきました。どちらの団子が売れるのかこれから楽しみです♪
くま組では、Kちゃんの「大きな山つくろうよ!」という提案で山づくりが始まりました。Nちゃんの「靴汚れるし、今日は暖かいけん、裸足になろ!」と言う声に2人は靴を脱いで並べました。そして、気が付くといつの間にかその横に10足以上の靴が並んでいて、砂場には裸足で気持ちよさそうに山作りをする子ども達でいっぱいになっていました。その中では、自然に役割が決まっていても、山の周りに海を作る係、山をパイプで転がして固める係、水をくむ係、それを男の子と女の子が「ここ掘って!」「水くんでこないかん!」と、てきぱきと動いているのです。私も、負けてはられないと一緒に山作りを楽しみました。今では、女の子が「さわらないでね」の表示をよく作っていましたが、今日は、初めて男の子が表示を書き、前回崩されて悔しい思いをしたことを思い出し、年少・年中児に「これ、読める?」と確認する姿がみられました。明日は、「山を火山にする!」のだそうで、どんな山になるのか楽しみです。一方、年少組のテラス前では、プレ年少児、年少児、年中児、年長児が入り混じってミニ発表会が行われていました。自分の踊った曲以外の踊りも覚えている子ども達は、曲がかかるとすぐに準備をして大声で歌いながら踊っていました。年少組のオペレッタ「まきばのパーティー」での、たんぽぽ組のNちゃんの動きに私はとても驚きました。始めは、観客席に座っていて「○○さんなら鳴いてみて♪」の時に立ち上がり手を大きく振り上げ「メーメー」など鳴き声を言っていたのですが、違う動きの子がいると「違う、違う!」と言ってより大きな動きをして、みんなに手本を見せていました。それは、まるで舞台監督のようでした。私も、年少・年中児の踊りも覚えてクラスの子ども達と一緒に踊って楽しみたいと思います。
コメント (「並んだ靴、裸足って気持ちいいね♪ くま組 中矢麻衣」 はコメントを受け付けていません)










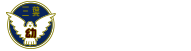

コメント (「避難訓練の意味」 くま組 原田寿子 はコメントを受け付けていません)