- blog
- album
- (089)-952-1777
- mituba@mituba.net
幼稚園の日記(ブログ)
2011年2月11日 金曜日
「明日はみんな笑顔で楽しく生活発表会に出ようね」と約束して迎えた今日。集合時間に市民会館のリハーサル室に、笑顔で「来たよ」と走って来るくま組の子ども達は、普段より声のトーンが高く、気持ちが高ぶっていたように思います。次々にやって来る友達を「あ、来た来た」と迎えに行く姿もあり、今日の日を心から楽しみにしていたんだなーと思いました。もちろんどのクラスも、どの学年も同じです。
それぞれの控室では、自分の出番までの間、プログラム紹介の練習をしたり、踊りや劇の部分練習をしたりして過ごしていました。年中、年長児のリハーサル室は、鏡張りになっており、自分達の姿を見ながら振付の練習をする姿も見られました。衣装に着替える時には「ドキドキする」と言う子。プログラム紹介の時には「うわー、緊張してきた」と胸を押さえる子。今日までの過程の中で、沢山のことを学んできた子ども達は、晴れの舞台に立って、自分達の力を十分に発揮している姿が、頼もしくもあり、嬉しくもあり、私もワクワクするものがありました。
《魔法の飴を手にのせて ハイ!!ポーズ♪》
今までの経験から得たもの、友達と協同的に取り組むようになれたこと、思いやりの心を持って人とかかわることができるようになったこと等々。今日のこの生活発表会で一人ひとりの育ちが確かめられる場になりました。
昨年年少組の時、舞台には上がっても歌ったり踊ったりすることができなかったH君は、年中さんになって、自分から少しずつやってみようとするようになりました。昨日は少し不安な面もありましたが、今朝、副園長と「頑張るよ」と指きりをして気持ちを高めると、一生懸命踊る姿が見られました。幕が降りるとやり遂げた満足した顔で副園長に走り寄り、抱きしめてもらっていました。子ども達一人ひとりを認めていくことの大切さを実感しました。
《年少・ひよこ・ぴよぴよ》
《年中》
連日年長組は、副園長から劇の内容は、自分達の生活が入っているものであることを教わってきました。くま組はリハーサル後に、いくつかの設定を変え、セリフや場面の流れがつながるようにしてきました。そのイメージが理解できた子ども達は、すぐに覚え、今日はおもいっきり役になりきって演じていました。どのクラスも、生活の場面が劇の中に入っており、満足いくストーリーになったと思います。この生活発表会は、保育の一貫であると副園長が常々話してくれています。私達教師は、この生活発表会までの過程が大切であることもふまえて、今後の活動に生かしていきたいと思います。
《年長》
この生活発表会では、沢山の方に協力して頂いています。舞台裏で、放送・幕・背景画・照明を担当して下さっている市民会館のスタッフ。三葉の子ども達を心から応援して下さっていて、温かく見守りながら、沢山配慮して頂きました。いろいろな方に助けられていることを実感する毎日です。
この生活発表会が終わったら、もうすぐ1年生になるとはりきっている年長児達。卒園までの日々を充実したものにしていきたいと思います。
*年長組は、最後の歌の後、沢山のアンコールを頂いて、「ビリーブ」を心を込めて優しい気持ちで歌いました。
もしも誰かが君のそばで、泣き出しそうになった時は、必ず僕がそばにいて、支えてあげるよその肩を・・・・
本当に優しく素敵な歌声でした。子ども達も感動!客席も感動!そして私達教師も感動! 本当にありがとう!!
2011年1月19日 水曜日
白い息をはきながら、元気よく登園して来た年長組の子ども達は、今日も戸外へ出て、寒さなんか吹き飛ばそうと、体を動かして遊んでいました。いつもは男の子ばかりがしているサッカーに女の子が加わり、らいおん組のYちゃんときりん組のHちゃんの姿がありました。転んでもすぐに起き上がり、ボールを追いかけて男の子にも負けていません。又くま組の3人組は木登りで、すたすたっと軽やかに登る姿は、やっぱり年長さんだなーと思いました。その様子を感心しながらカメラを向けていると、「先生、僕達も撮って」という声がしました。振り向くと、ひよこ組の三輪車軍団が、得意げに列になってこちらを見ながら走っていました。もうすぐ年少組さんになる子達、まあなんとたくましいこと。これからが楽しみです。
又、昨日に引き続き、青コースの年少・年中組は、屋外遊ぎ場へ行っておもいっきり凧揚げを楽しみました。風にのってよく揚がったという話から、昨日の物より大きい凧を作って持って行くと、あがる!あがる!空高く飛ぶ凧に子ども達は大喜びでした。広い場所でのびのびと遊ぶ環境があることが、とても幸せなことだと思いました。
年長組は、各クラス発表会の劇の準備がどんどん進んでいます。大道具作りはもちろん、自分達が使う物を毎日少しずつ工夫して作っています。5クラスがお互いに練習風景をこっそりのぞいてみたり、セリフの発表をしたりして、刺激し合って、明日はここまで進めようと子ども達の意欲が高まりつつあります。くま組は、今日こそ初めから終わりまで通してしようと決めていたので、みんないつもより早く行動することができていたように思いました。
又、来週25日には、卒園DVD収録があります。5クラス全員が揃って活動するものとしては、卒園式を除いて最後になります。三葉幼稚園で過ごした月日の中でできた沢山の思い出を、このDVDの中に収めていきます。それぞれの時期にしたこと、楽しかったこと、頑張ったこと、学んだこと、そしてここで沢山の友達に出会えたこと、いっぱいいっぱい思い返しながら語ります。卒園まであと2カ月になりました。これからの毎日毎日が、とてもとても大切な日に思えます.この子達の輝く瞳を忘れないよう、心に刻んでおきたいと思います。
コメント (「卒園まであと2カ月」 くま組 原田寿子 はコメントを受け付けていません)
2010年12月7日 火曜日
サンタクロースの衣装を身にまとったくま組・らいおん組・きりん組3クラスが、デイサービスと介護施設「合歓の木」を訪問しました。今回が年長組としての訪問は最後になりました。子ども達は、今まで交流して下さったお年寄りの皆さんに感謝しつつ、触れ合うことを楽しみに練習してきました。このデイサービス、老人施設訪問で子ども達は、沢山のことを学びました。もうすぐ1年生になることを胸を張って堂々と発表することを目標にして、幼稚園の遊びを紹介したり、楽しかった出来事を話したりすることにしました。訪問をするにあたって大切なことは、それまでの過程の中で、子ども達の心が育つことと相手に対しての態度や礼儀を知ることだと副園長から教えてもらっていたものの、十分に子ども達は、自分の力を発揮することができたのだろうかと、反省点も多く残りました。
人前で相手を気遣いながら、大きな声でわかりやすい言葉で発表することは、2月に行われる生活発表会にも生きてきます。相手の方の反応を見て更に自信を持ち、自分の役割を果たしていくことも重要なポイントになります。
くま組は、昨日の練習で元気さが足りず、副園長は、「あわてんぼうのサンタクロースではなく、ねぼけたサンタクロースになりそうよ」と笑わせてくれました。今朝は早く登園してきたので、戸外で体を動かして遊んだ後、焼き芋を食べ、体も心もお腹も温まったところで、シャキッとして1度だけ練習をしました。今まで声が小さかったYちゃんもしっかり大きな声で名前を言うことができて、友達も大喜びでした。
合歓の木に着くと、事務所の方や先生方が温かく迎えて下さり、エレベーターに乗って3階へ・・・・・長広い部屋に20人のお年寄りの方々が、今か今かと待って下さっていました。サンタクロースの服と帽子を身につけて登場した子ども達を見ると、「かわいいのー」と笑顔で言って下さり、子ども達も気分が乗って練習の成果を十分に発揮することができました。お店屋さんの紹介では、作品展・バザーでした時のように、大きな声で発表し、合奏ではそれぞれの楽器を楽しく演奏したので、1番だけの予定を2番までに伸ばしてみました。すると、「上手やね」と声を掛けてもらい、子ども達も満足していたようでした。帰る前に、今日作ってきたお店屋さんごっこの品物をプレゼントしようとHちゃんが発案し、一人ひとりと握手をしながら渡していきました。
この施設訪問で学んだ人への思い、感謝、喜び、そして人の温かさなどを小学校へ行っても、中学生になっても、そして大人になっても忘れずにいてくれることを願いながら帰ってきました。
1月からは年中組さんにバトンタッチします。 今まで沢山の方々と交流できる場を与えて頂いたことに感謝したいと思います。
9日(木)は、ケアフル竹原にぞう組が。歩風里にくじら組が訪問します。素敵な思い出が作れますように・・・・・
コメント (「小さなあわてんぼうのサンタクロースがやってきた」 くま組 原田寿子 はコメントを受け付けていません)
2010年11月29日 月曜日
冷たい風がピュピュー吹く中、朝早くから教師、保護者がいそいそと準備を進めていきました。あらゆる所からとても良いにおいが漂っているなか・・・小さなお店やさんもせっせせっせと開店準備。さあ!いよいよ待ちに待った作品展・バザーのスタートです。
開門と同時にたくさんの方が目に付いたコーナーに一目散。園庭では教師たちの子どもの店と喫茶、後援会からバザー、会議室では即売会が行われていました。教師の喫茶では、今年一押しのメニューのひとつ!にらみそ付きのおにぎりセットをはじめ、体の中から温まる豚汁、キッズフェスタでお馴染みの芋アイス、小さな子も食べやすい蒸しパン、わたがし、コーヒーを販売していました。教師の顔を見て嬉しそうに買いに来て「おいしいね」と食べている子どもの姿がたくさん見られて、作ってよかったなと思いました。子どもの店では、初めてお買い物をする年少児の姿がたくさん見られました。じーっと商品を眺めた後、50円の品物を選んだ年少児が「10円、20円、、、」と一つ一つお金をならべながら数える姿に「茶色のお金だよ。」とそっと声をかけ、見守るおばあちゃんの姿に、このようにすこしアドバイスしながらも待つ姿勢が子どもを育てるのだと思いました。長い時間かけて出したお金で買った商品を大切に持って帰る姿はちょっぴり大人になったように思えました。
お昼時には、後援会から出店されていたうどん、カレー、おでんなどを家族揃ってわいわい食事をする光景は、寒さを忘れるほど温かい気持ちにさせてくれました。
壁にまるで風に散っているかのように貼られた落ち葉。その舞っている落ち葉に吸い込まれるように駆け上がる階段の先には、世界にたった一つしかない大切な作品が展示されていました。我が子の作品をじーっと見て「ふふふっ」と笑うお父さんお母さん。「ここはこうなるんよ!」と一生懸命作った作品をアピールする子どもの姿がどこでも見られました。見に来ることの出来ない家族に見せようと、写真を何枚も撮る方もいらっしゃいました。子どもたちの作品や絵は、どれも楽しんでいる姿が想像でき、とても感動しました。
「いらっしゃーい!いらっしゃーい!いかがですかー?」とどこのテントにも負けないほど、威勢の良い掛け声。通りすがりの人も何だろう?と足を止め、立ち寄って覗きにきます。「銀行はあちらです。」とまずは、言われるがままに銀行へ行くお父さん、お母さん、そして子ども達。転入してきたH君も、銀行でしっかり働いていました。たくさんあるお金の種類の中から、窓口から指定されたお金を一枚一枚探すのに時間がかかり、あっという間に行列です。しかし、一人一人に「ありがとうございました!」と深く頭を下げてお礼を言う姿を見た保護者の方もとても感動していました。おもちゃやさんとおすしやさんでは朝早くから絶え間なく子ども達の声が響いていました。持ち場のお店だけではなく、隣のお店へ行って手伝ったり、買い手になってみたりと楽しむ姿が見られました。自分でラッパを作り呼び込みをするMちゃん、鉄板でやきそばを作るH君、年長児がいなくなったすきに店員になり売り込みを始める年少児、長い時間にぎわった子どもたちのお店やさんでした。大人たちと一緒の園庭で大きなテントの下にどんっと構えていた子どものお店やさんは、とても頼もしく、また、嬉しそうに見守り、一緒に楽しんで買いに来る家族やお客さんからたくさんの喜びをもらった子どもたちは、今日も幸せな一日になったことでしょう。作品展までに成長を見せてくれた子どもたち。これからが楽しみです。
コメント (「作品展・バザー」 くま組竹田 佳那子 はコメントを受け付けていません)
2010年11月12日 金曜日
今日は遠足。夜中から降り出した雨が心配でしたが、少々の雨なら行けると思っていたところ、出発する頃には、太陽が雲間から顔をのぞかせ始め、三葉の子ども達の為に晴れてくれたような嬉しい気持ちで、バスに乗り込みました。行きは、青コースが大型バスで行き、赤コースは、それぞれのバスで乗り合わせて行きました。「動物達は、きっと雨上がりの外で遊ぶことが好きだから、沢山出てくれていると思うよ」という話をすると、「早く着かないかなー」とバスの中でもワクワクしているようでした。
今回の遠足は、園の教職員全員で行きました。例年は、役員さん方にも同行して頂いていましたが、子ども達がしっかりしているので、教師の子ども達に対する配慮の仕方や、現場での保育に対する姿勢や在り方を考えるチャンスになればということで、内々でしっかり連携をとって頑張ることになりました。運転手さんや預かりの先生達、事務職員も含めて、子ども達の遠足をより良いものにする為に一致団結することもできました。
園内では、学年単位で行動することとし、他のクラスの友達と手をつないでまわるようにしたことで、いつもとは違った意識の持ち方ができ、学年内でのコミュニケーションが子ども達も職員達もとることができました。教職員の連携の取り方にも良い影響が見られました。
今日の動物達は、予想通り、雨上がりの動物園はにぎやかで、ほとんどの動物が外へ出て、元気よく鳴いたり、歩いたり、泳いだりする姿が見られました。新しくリニューアルされたペンギンのコーナーでは、きれいなガラス張りの水槽の中をペンギン達が、スーっと泳ぐところが目の前で見えることに、みんな大喜びでした。ライオンは残念ながら、フロアーの改築中で、見ることができませんでしたが、キリンやしまうまが近くまで寄ってきてくれたことで、アフリカンストリートもにぎわっているように思いました。サルのコーナーでは、赤ちゃんがお母さんのオッパイを飲んでいる様子を見ることができ、子ども達は、自分の小さかった時のことと重ね合わせて、にこやかに見ていました。
待ちに待ったお弁当は、待ちきれなくて年少組が1番に食べ始めました。今回、全員が揃って食べるということで、どうなるだろうと不安ではありましたが、いざ年中、年長も加わって食べ始めると、それはそれは素敵な場面になりました。今まで園内でも、400名以上の園児達が、一同に食したことはなく、とても嬉しい時間でした。又、バスのおじちゃん達が、輪の中に入ってくれて食べたり、預かりの先生達が一緒にまわってくれたことが、子ども達はとっても嬉しかったようでした。
年長組は時間に余裕があり、いつも通らないポニーやロバのコーナーへも行きました。ロバの耳はびわの葉とよく似ていたし、ひつじやヤギのウンチは、うさぎのウンチのように小さくてコロコロなことに気付きました。又、オウムのタロー君が「おはよう」としゃべってくれたことで、年長組(教師達も)は大興奮でした。またその時丁度12時30分で、からくり時計が動き出し、音楽隊が出てきて、ステキなメロディーを奏でてくれました。
サルは、「キーキー、ウォーウォー」子ども達を見て叫び続け、圧倒される場面もありましたが、いろいろな動物の生態や鳴き方、生活の仕方がわかり、素晴らしい遠足になったと思います。
プレ年少さんも年少組さんも、最後まで自分達で頑張って歩くことができました。きっとお家でも、今日の遠足のことが話題になることでしょう。ちなみに年長組は、いろいろな動物達のウンチの大きさや色、形を覚え、どうしてそんなウンチなのか、図鑑等で調べてみることにしています。
コメント (「雨上がりが大好きな動物達」 くま組 原田寿子 はコメントを受け付けていません)
2010年10月15日 金曜日
秋晴れの中、年長組は稲刈りとさつま芋掘りに行きました。昨年、稲刈りに時間がかかったという反省点から、昼食を農園で食べたらいいという副園長のアイディアで1日の長い園外保育となりました。
稲刈りに行く前に昨日の赤コースの子ども達がしたように、青コースの園内稲刈りをしたことで、年長組は稲刈りへ行くことへの期待も膨らんでいるようでした。副園長から植えた時は苗、それから育って稲になり、収穫して稲木にかけて天日に干し、もみを取ると玄米になる。もっと皮をはぐと白米になり、全ての米を取った後はわらになるという過程を教えてもらいました。捨てるところがなく、利用価値のある物であることがわかり、年少、年中組さんも興味津々で聞き入っていました。
園内の稲木を見て出発した年長組の子ども達は、高木農園に行く道中にも、稲木にかけられた米を見つけ、鳥に食べられないようにネットをかぶせてあることや、ハトが食べにきている様子を見つけ、米が食べられたら大変だと話し合っていました。稲刈りが始まる前にみんなが植えた4本の苗が何本になっているか、副園長と一緒に数えてみると、なんと36本の束になっていました。4本が36本になることは9倍に頑張って成長したんだということに気付いて、自然の恵みのすばらしさにも気付くことができました。
刈り方は昨日から習っているので、やり始めると自分で束をつかみ、要領よく鎌を引いて刈って行く姿が見られました。1人3株を刈り取り、2人分(6株)を1本のひもでくくり、稲木ににかけて行きました。機械で刈ることにも挑戦させてもらい、おいしいお米になることが待ち遠しいと話す姿が見られました。
稲刈りの後は、今日のお楽しみの「ランチタイム」です。朝から副園長の手作りニラみそのおいしい香りに「早くお昼ご飯が食べたい」と言っていた子ども達。さつま芋畑に広げられたブルーシートの上で麦ごはんのおにぎり(のりつき)ときゅうりのニラみそ、そして今日のビッグメニューはししゃもです。こんがり焼いたししゃものおいしいこと。おかわりはないかと猫のように残ったししゃもの前で見つめるくま組の子ども達の様子にみんな大笑いでした。
そしてもう1つ、昨日掘ったお芋のスティック揚げ。ここで副園長からすごいお話が・・・昨日のお芋をおいしくいただこうと揚げたけれども、先月まで食べていたお芋に比べると甘さがありませんでした。その理由は、掘った芋は数日天日に干してから保管します。それは単に乾かしているのではなく、土の中で育ったさつま芋には水分が多く含まれているので、甘みが少ないのです。それをお陽様に当てて乾かすことで、水分が少なくなり、甘さを凝縮しているのだそうです。だから焼き芋をする時のお芋はとても甘くておいしいのです。更に上手に保管すると、日が経つごとに甘さは強くなっていくのです。このことに気付いて欲しいと副園長は、私達教師に話してくれ、子ども達にも伝えていくよう指導を受けました。
お腹がいっぱいになった後は、いよいよさつま芋掘りです。副園長の手伝いをクラスから2人ずつ募るとどのクラスも我よ我よと名乗り出してダッシュする姿が見られました。年長組は最後まで自分達の手で掘ってみよう・・・と決めていたのですが、なかなか田んぼの土は固くて時間がかかりました。大きなお芋、中くらいのお芋、小さいお芋の大きさは自分で見て仕分けをしなさいと言われた子ども達は、よく考えて分けていました。今日の副園長の話をしっかり聞いた子達は、食べることを少し先延ばしにして甘くなったお芋を食べるのではないでしょうか?
お陽様の力はすごいですね!! 水コースのこあら組さんもお芋掘りを親子で楽しんでいました。どんなお料理に変身するのかな?
コメント (「稲刈り・さつま芋掘り・そして楽しいランチ」 くま組 原田寿子 はコメントを受け付けていません)
2010年9月16日 木曜日
今週に入ってから、砥部焼の絵付けに行くことを楽しみにしていた年長組の子ども達は、どんな絵を描こうかと下書きから念入りに考える姿が見られました。一生の宝物になるこの砥部焼の絵皿は、毎年年長児が三葉幼稚園の卒園記念の1つとして制作していて、卒園生の宝物になっています。25年前から始まった砥部焼の絵付けですが、毎年出来上がった絵皿は作品展に展示して、沢山の方々に見てもらった後、卒園式まで大切に園で保管しておきます。いよいよ今年は、自分達の番だとはりきって準備をし、出発前の副園長からの諸注意等を真剣に聞くと、約45分の道のりを心弾ませて行きました。
砥部焼観光センターに着くと、今か今かとセンターの方が待っていて、早速案内して下さいました。店内を通って2階の絵付けコーナーに行く途中、店員さんやお客さんに副園長との約束通り、大きな声で挨拶をしながら歩くクラスと、挨拶ができないクラスがあり、就学前の子ども達の生活の中での課題となりました。これからも園外に出向く機会もあります。公共の場での言動等も指導していきたいと思います。
2階に上がると、予約席が設けてあり、136名(1名欠席)が一斉に座ると、センターの方から絵付けの仕方を教えて頂きました。筆の使い方、液の混ぜ方、描き方を聞いた子ども達は、おそるおそる筆を液につけると、一気に描く子、悩みながら描く子と様々でしたが、世界に1つだけの大切な砥部焼になることに期待を持って仕上げることができました。
その後は、観光センターの作業場をクラスごとに案内して頂きました。原石を砕いて粉にします(砥部焼は石の粉から作ります)その粉に水を入れて混ぜ合わせ、粘土にします型をろくろにのせ、粘土を貼り付け、余分な所を切り取って形を作ります乾燥したお皿に絵付けをします真っ白な上薬を塗ります最後に窯に入れて18時間焼きます 真っ白な上薬を塗ると真っ白になって絵が見えなくなるのですが、焼いていくうちにガラス状になり、出来上がった時には、絵が浮き上がり光沢のある絵皿になります。この行程を教わった子ども達は、更に自分達の絵皿ができることが楽しみになり、「明日できるの?」等、気の早い話もしていました。
この原石は230年前から、砥部町の一番高い三角の山で採掘していたそうですが、そこでは採れなくなり、今は広田村の山から採っているそうです。愛媛の特産品である砥部焼に関わることができることは、地元に生まれて育っていく中で、とても有難いことだとも思います。原石がいつまで採れるのか、園児達が大人になった時にもあるのだろうか?と気になりながら帰りました。ずっと砥部焼が存続しますように!!
コメント (「世界に1つだけの大切な砥部焼」 くま組 原田寿子 はコメントを受け付けていません)
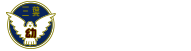

コメント (「素敵な1日!生活発表会」 くま組 原田寿子 はコメントを受け付けていません)