- blog
- album
- (089)-952-1777
- mituba@mituba.net
幼稚園の日記(ブログ)
2015年2月11日 水曜日
今日は、平成26年度の生活発表会がありました。三葉幼稚園の発表会は、お遊戯会や音楽会とは違い環境による教育の中で体験してきたこと、お絵描きや制作、友達と協力することなど全てを折りこんだものになっております。又、本番では子ども達が主役です。教師は、子ども達が伸び伸びと表現できるよう、サポートするのみです。「自分の身は自分で守る」教師が届かない部分も、子ども達が何気なく補ってしまう、そのような力を1年間を通して身に付けた子ども達は、今日も舞台の上で伸び伸びと表現することができていました。
保育所ぴよぴよの子ども達は、たくさんのお客さんを前にしても年長のお姉さん達と一緒に踊ったり、リズムに合わせて体を動かすことができていました。
満3歳児のひよこ組は、大きな舞台の上でも、堂々と大きな声で元気よく歌ったり踊ったりしていました。始まる幕の裏側では、教師が豚さんのお家の屋根をはずしておくことを忘れていました。それに気づいたHくんは、幕が上がる直前に屋根をぱっと取り付けていました。又、副園長の話しをしっかりと聞いて、列に並ぶ姿に成長を感じました。
年少のオペレッタでは、CDの曲を聴いて台詞をしゃべったり、それに合わせて体を動かしたりと曲を覚えて楽しそうに表現していました。演技中、自分の位置が分からなくなっていたAくんに気付いたBちゃんが手を引いて位置に戻してくれました。共に生活する中で、友達を気にかけて思いやる気持ちが育っているなと感じる出来事でした。
年中は「楽しく元気よく」を目標にやってきました。手をしっかりと伸ばして振り付けをみんなと合わせて元気いっぱい表現することができました。オペレッタでは、友達の足が当たって泣き出したSくんをTくんが慰め、その後も気に掛けて助け合いながら、終えることができました。あと1か月で年長になるという自覚が感じられました。
年長の劇は、3年間の幼稚園生活の総まとめです。台詞のやり取りや大道具の準備などは自分で考え、全て自分達で進めていきます。今日も、劇中に大道具が壊れると舞台袖から教師にガムテープをもらって、なんとか直して舞台に戻ったり、トラブルも自分達で解決したりして力を合わせてやり遂げることができていました。今年1年、「踏み出そう、はじめの一歩」を目標にしていた年長児ですが、「はじめの一歩」を歌い、小学校に向けても力強く進んでいくことを誓いました。アンコールでは、大好きなお父さん、お母さんへ「この広い野原いっぱい」の手話をプレゼントし、会場に大きな感動を与えてくれました。
環境という教育の中で育んできた力を生活発表会の舞台の上で存分に発揮してくれ、私達教師も子ども達からたくさんの感動をもらった1日でした。生活発表会を見に来て下さった皆様、ありがとうございました。
2015年1月20日 火曜日
先週から事務所横の水槽の水替えをしようと思っていたのですが、すっかり週が変わってしまい、今日になってしまっていました。早く登園してきたくま組の子ども達の手を借りて、水槽の掃除をしました。水槽では、保護者の方から頂いた鯉と副園長が持って来てくれた5年程生きているどじょうを飼育しているのですが、子ども達はすばやく逃げる魚達を捕まえるのに苦戦していました。子ども達はどうすれば上手く捕まえることができるか意見を出し合いながら、魚との知恵比べが続きました。無事に魚を水槽からバケツに移すと、水槽を洗い始めました。水が掛かると「冷たーい!」と大はしゃぎしていました。しかし、しばらくするとAくんが、「先生、水が温かくなった。」と気付きました。そして、他の子ども達も水に手を入れて、「本当や!温かくなっとる!」と喜んでいました。なぜ、水が途中から温かくなったのか?それは、幼稚園には水道水と井戸水の蛇口があって、子ども達は井戸水を使って水槽を洗っていたのでした。寒い季節が子ども達に、水によって水温が違うことを気付かせてくれたようです。
昨日の私達年長担任の反省なのですが、3学期が始まってからすぐ、副園長から「卒園DVDの収録に必要な物は、忘れずに持ってくること」と声を掛けてもらっていたのですが、昨日になっても持ってくるのを忘れている子がいて、全員が揃えることができていませんでした。副園長から「小学校に就学するまでに、子ども達には自分で準備するという意識を持たせることが大切だ」と指導を受けた私達は、本当にその通りであり、自分たちの意識の低さを反省しました。今日の練習でも、忘れていた子がいたのですが、小学校では宿題や次の日の準備など、自分でしなければならないことがたくさんあることを副園長に話してもらい、子ども達の就学に対しての意識が高まったように感じられました。また、三葉幼稚園の制服は、どの子も似合う色や柄で1番素敵な服だという話もしてもらいました。幼稚園の制服を着て登園できるのも、あと2ヶ月です。「汚れても、毎日着ておいで。」と優しく副園長に声を掛けてもらって、残りわずかな幼稚園の行事に意識をもって参加できるよう励まされて、年長児は大きくうなずいていました。
ぱんだ組は、初めて施設訪問でケアフル竹原に行きました。子ども達は、「ドキドキする。」と言って少し緊張気味でしたが、「おじいちゃん、おばあちゃんが一緒に歌ったり踊ったりしてくれて嬉しかったよ。」と満足そうでした。 

コメント (「自分のことは、自分でする」 くま組 丸山利夫 はコメントを受け付けていません)
2014年12月4日 木曜日
今日は、赤コースの年長・年中組がイヨテツスポーツセンターにアイススケートに行きました。昨日のブログでも紹介されていた落ち葉焚きの経験のように、氷に触れるという経験も子ども達には自然現象を感じることのできる貴重な体験です。アイススケートには、自然現象を感じること以外にも、「自分の力で歩いたり滑ったりすることができるようになることやスケート場でのルールを守って危険なことをしない」等のねらいがあります。副園長から、「自分の靴のサイズを伝えて靴の中に物が入っていないか確認すること。靴の紐を優しくほどいたら靴のべろをしっかりと引っ張って靴を履いて準備をしておくこと。」等、自分でしておかなくてはならない課題をもらいました。スケート場では、カワイ体操教室の上野先生・近藤先生にスケートの滑り方を教えてもらいました。準備体操を終えると、小さいスケートリンクをハイハイで進んでいきました。子ども達は、「冷たーい!」と友達と顔を見合わせて氷の感触を楽しんでいるようでした。
大きいスケートリンクに移動すると、手すりにつかまって足踏みの練習をしました。「1・2.1・2.」と元気よく数を数えながら氷に足を慣らしていきました。そして、いよいよ氷の上に立つ練習です。まずは、転び方が大切でお尻から転んで、起きる時には赤ちゃんのポーズになります。そして、片足を立ててカエルのポーズからペンギンで立ち上がります。初めは恐る恐る立ち上がっていた子ども達でしたが、慣れてくるとスムーズに立つことができるようになりました。子どもの中には、助走をつけて滑っている子もいて、教師よりも上手に滑れることに驚かされました。スケート場の中は、息が白くとても寒かったのですが、1時間たっぷりと滑って、自分で立つことができた達成感を感じている子ども達は、にこにこの笑顔でした。
体の芯から冷え切っていた子ども達は、バスの中で温まっていたものの、もっと温かくなる素敵なものが待っていました。それは、手作り給食でした。今日の手作り給食はおでんで、大根・じゃがいも・こんにゃく・厚揚げ・ちくわと具沢山で体をぽかぽかにしてくれました。
明日は青コースの子ども達がアイススケートに行きます。明日も子ども達の素敵な笑顔が沢山見られると思います。
コメント (「アイススケートに行ったよ!」 くま組 丸山利夫 はコメントを受け付けていません)
2014年11月10日 月曜日
金曜日のブログの写真を見た副園長は、とても残念な気持ちになったそうです。それは、土粘土をしている写真だったのですが、粘土板を一列に並べて子ども達が向き合って座って同じ程度の量の土粘土をもらって一斉に作っている姿でした。その時間、副園長は留守だったので、ブログを見てそのことを知ったのでした。三葉幼稚園の保育の良さは異年齢児が遊びを通じて自由にかかわり、たくさんの刺激を受けることです。しかし、金曜日のような一列に並んだ状態ではかかわりが制限され、小さな粘土板の上ではダイナミックな遊びはできないということでした。大量の土粘土を戸外に出し、大きな板の上で作るという環境は、副園長の「たくさんの子ども達が刺激を受け合いながら気づいたりダイナミックな作品を作ったりしてほしい」という意図があるにもかかわらず、私達教師はいつの間にかそのことを忘れていたのでした。三葉の教育には、教師の一人一人違っていい、自分を表現する場をできるだけ多く作るゆとりと大きな心が必要です。そのためには、教師みんなが連携し、おかしい所や教師の都合だけで動かさないことを意識し、フォローし合うことをもう一度話し合いました。
今日は、毎年この時期に行っているサニーマートに買い物に行きました。消費税が8パーセントに上がり、100円では買い物が難しいのではないかと心配していた副園長は、サニーマートの店長さんと話をしてくれ子ども達が自分達で考えながら買い物ができる準備をしてくれました。買い物には年長・年中が混合で5人グループを作り、グループで相談しながら買い物をします。100円という金額内であれば、何袋買ってもいいことや表示が100円の物でも消費税がかかってくることなど、考えなければならないことがたくさんありました。サニーマートに着いた子ども達は、お店の人やお客さんに元気よく挨拶をして店内を見学しました。今日は特売日で100円以下の品物が多く並んでいて、子ども達は品物の並べ方や値札の表示の仕方など発見したことがたくさんあったようです。お菓子は10円から100円を超えるものまでありましたが、価格表示も今年は外税になっていて、その見方も教わっての買い物です。それぞれのグループが100円に収まるように考えて選ぶことができていました。税込94円の品物は102円になり、通常は100円では買えないのですが、実は袋を持参すれば2円引いてもらえることを副園長から教えてもらい、エコカードを提示している子もいました。この2円は貯金され、以前サニーマートさんから頂いた絵本のように近隣の保育所や幼稚園に送られるそうです。買ってきたお菓子は、午後に年少さんやひよこさん、ぴよぴよさんも招待して、みんなで分け合って食べました。
各グループリーダーには、もうひとつ大切な役割がありました。今日100円をもらって買い物をしたことを副園長に報告することでした。「102円のお菓子を買いました。袋を持っていったので2円安くなって100円で買いました。おつりはありません。」などと言ってレシートを渡します。「22円のお菓子を4個と11円のお菓子を1個買って、3円おつりです。」などなど、みんなよく考えて買い物ができました。子ども達も教師も「買物の仕方、社会的ルール、計算をすること、責任をもって報告すること、グループで相談すること、グループがまとまること、アレルギーの友達への心遣い」いっぱいいっぱい感じたり学んだりした1日でした。
コメント (「サニーマートに買い物に行ったよ!」 くま組 丸山利夫 はコメントを受け付けていません)
2014年10月17日 金曜日
三葉幼稚園では、本物の野菜と包丁を使ってままごとをするコーナーがあります。サニーマートさんのご好意によっていらなくなった野菜を提供して頂き、子ども達は楽しい生活を送ることができています。昨日の話になりますが、昨日は先日まで豊富にあった茄子や白菜、きゅうりや人参など季節の野菜がそろそろ終わりになり、少なくなっていました。子ども達は少ない野菜を切ったり並べたりして料理を楽しんでいましたが、野菜はすぐになくなってしまいました。そのことに気付いた副園長は、駐車場の畑からさつまいものつるや野花を採ってきました。副園長はさつまいものつるを手に取ると、つるの皮の部分を残して交互に折って、ネックレスを作りました。ネックレスを作りたいと集まってきた子ども達の中には、時間がなくて作れなかった子もいて、「明日作る!」と言って降園しました。そして、今日は朝からさつまいものつるを用意していると、昨日作れなかった子ども達が集まってきました。つるを折って作る方法を伝えると、子ども達はつるが折れる時の「ポキポキ」といった弾けるような感触が心地よくて、つるを折る度に友達と顔を見合わせて嬉しそうに作っていました。なかにはさつまいもの葉に花を飾る子もいて、ネックレスやブレスレットを作って楽しんでいました。秋の紅葉はまだまだ遠く感じますが、周りに目を向けると秋を感じさせてくれる自然物があることに気付かされました。秋の訪れと共に、自然物を使った遊びを子ども達と存分に楽しみたいと思いました。
今日は、年長児が高木町にある農園に稲刈りに行きました。園内の稲刈りでは、水と栄養不足で十分に実らなかった稲を見ていた子ども達は、「高木の農園は、きっと大きくなっている!」と楽しみにしていました。農園に着くと副園長が稲を一株刈って、何本あるかを子ども達と数えていきました。数えた株は47本あって、幼稚園の稲の4倍もあったことに驚いていました。そして、「なぜ、こんなに大きく生長したのか」を考えることにしました。幼稚園の稲はバケツで栽培していたので、限られた水と土しかなかったことをよく覚えていました。農園の稲はたくさんの水と土があるから育ったのだと納得できたようでした。運転手や教師が傍について自分で稲を刈っていくと、副園長との約束を守って、自分の力で稲を刈っていきました。大きく育った株は手ごたえがあって、ザクザクと良い音をさせながら、三株ずつ刈っていきました。刈った株は役員さんに束ねてもらったり、稲刈り機で稲を刈る経験もさせてもらったりして貴重な時間を過ごすことができました。稲木に干す場面では、教師の反省がありました。稲木を組んで干していくと、稲の重みで稲木が沈んでお米が地面についてしまっていたのです。それに気付いた田んぼを管理してくださっている遠藤さんに、「こうした失敗を子ども達に伝えることが大切だ。」と声を掛けてもらって、教師の失敗からもう一つ学ぶことができた子ども達でした。
地域の方々のご好意で貴重な体験をさせてもらっていることに感謝の気持ちをもつことを忘れず、更に良い保育ができるように心掛けていきたいと思いました。
コメント (「稲刈りに行ったよ!」 くま組 丸山利夫 はコメントを受け付けていません)
2014年9月18日 木曜日
最近、くま組では運動会の練習の合間をみて、廃材遊びをよくしています。運動会の組体操のグループ等で仲良くなったことで、今までは男の子達が中心となっていた遊びに女の子達が入るようになりました。毎日こつこつと作っているのはピタゴラ装置でした。ラップの芯を半分に切ってつないで、球が転がる道を作ると、上手く転がるように廃材を積み重ねて高さや傾斜を調整して工夫しながら作っていました。そこに女の子達が加わるとピタゴラ装置の周りに家やお風呂等ができてきて、街のイメージが広がってきました。限られた時間の中でも、自分達のしたい遊びを見つけてお互いを認め合いながら満足な生活を送っている子ども達の姿に、夏休みを終えて一回り大きく成長していることを感じることができました。
今日は、悲しいお知らせがありました。園内で育てていた稲が枯れていたのです。全クラスの子ども達が集まって、「なぜ枯れてしまったのか?」副園長と考えていきました。まず、枯れてしまった原因は、水が全くなかったことでした。園内の稲はバケツやプラスチックの容器の中で栽培しているため、どこからも水を得ることができなくなった稲は枯れるしかなかったのです。乾ききったバケツの中の土を出してみると、根を隅々まで張り巡らせている様子がよくわかりました。白く乾いた土の塊を見て、「可哀そうなことをしてしまった。」と子ども達は感じたようでした。枯れた稲の中には、まだ緑色の稲もあったので、水をあげて様子をみるか、このまま刈ってしまうか多数決をとることにしました。すると、子ども達からは「水をあげて様子をみる。」という意見が多く出ました。子ども達と今後の稲の様子を観察していきたいと思います。
くじら組とぞう組は、歩風里とケアフル竹原を訪問しました。そら豆音頭を踊ったり、歌や手遊びをしたりして楽しんだ後、一人ひとりが夏休みに楽しかった思い出を絵に描いて発表して、お年寄りに大変喜ばれました。そして、お土産を園に持ち帰ると、幼稚園のみんなで分け合うことにしました。各クラスに持っていくと、事務所の副園長や事務員さんにも「みんなで分けてください。」と言って持って行きました。そこで副園長は、「みんなで分けるって誰の事?」と聞きました。事務所には3人いるので、平等に分けるためにはどうすればいいか、かなり考えたようでした。その中で、1つの物を3つに分けることが難しく、4つに分けるのは簡単なことを話したそうです。手紙を折った時の経験がここで生きていることに驚かされました。ちょっとしたきっかけ作りが、子ども達の頭を働かせる楽しい時間になることも忘れないでおきたいと思います。
コメント (「稲の栽培から学ぶこと」 くま組 丸山利夫 はコメントを受け付けていません)
2014年6月30日 月曜日
先週のブログで園内の田んぼのカブトエビが紹介されていましたが、先週の金曜日に新しい生き物をくま組の男の子達が捕まえていました。捕まえた生き物は、魚のような尻尾があって、お腹にはエビのような足がたくさんありました。また、泳ぎ方も変わっていてお腹を仰向けにして泳いでいたのです。子ども達は興味津々で、急いで図書館にある図鑑を調べ始めました。しかし、いくら探しても見つからず、金曜日は降園することとなりました。そして今朝、男の子の中でも1番張り切っていたKくんが、「先生!わかったよー!」と駆け寄ってきて、ポケットから小さな手紙を出して言いました。「あの生き物、ホウネンエビっていうんよ!かつお節を食べるけん、持ってきたよ!」と自慢気です。Kくんの呼び掛けに男の子達が集まってきて、かつお節に寄って来るホウネンエビを嬉しそうに眺めていました。子ども達は日々、新しい発見や気づきがあり、そのことを楽しみにして幼稚園にやって来ます。図鑑で調べることは探究心へとつながり、こうした過程が小学校の学習の芽を育てていくのです。
今日は、プール開きの日でした。日中はぐんぐん気温が上がって最高のプール日和になりました。戸外で子ども達が普段よく踊っている「エビカニクス」等の曲を元気いっぱい踊りました。火照った体にプールの水はとても心地よくて、子ども達は存分にプール遊びを楽しみました。プール遊びでは、水遊びを楽しむ以外にも、たくさん学ぶことがあります。プールでのルールを守って安全に楽しむのはもちろんのこと、楽しむのは自分一人だけではなく、周りの人のことも考えながら楽しむことが大事なのです。例えば、体を拭くタオルを掛けることですが、タオルを大きく広げたまま掛けると、みんなのタオルを掛けることができません。そこで、タオルを細く折って掛け、みんなが掛けられるように工夫するのです。水に親しんで友達と水遊びを楽しむ以外にも、周りの人への心遣いも育っていくのです。昼食は、役員さん手作りのコロッケでした。役員さんの愛情がたっぷり詰まったコロッケは、とてもおいしくて2つともぺろりと食べてしまいました。その他にも夏野菜を使った料理も添えられて、心も体も大満足の子ども達でした。さすが三葉幼稚園の役員さん方、手際よくてきぱきと進めて下さって、子ども達は大喜びでした。
午前中に、サニーマート衣山店の店長さんが素敵なプレゼントを届けて下さいました。それは、お客さんが買い物袋を節約して下さったお金で、購入して頂いた絵本でした。店長さんから、その話を聞いた子ども達は、「うちのお母さんもしよったよ!」と、少しずつ無駄を省いていくことで新しい物が買えることを理解したようでした。物が溢れかえる現代には、こうした節約する取り組みや経験が未来を生きる子ども達には、とても重要なのだと感じました。
コメント (「今日はプール開き!」 くま組 丸山利夫 はコメントを受け付けていません)









































































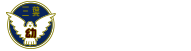

コメント (「生活発表会があったよ!」 くま組 丸山利夫 はコメントを受け付けていません)