- blog
- album
- (089)-952-1777
- mituba@mituba.net
幼稚園の日記(ブログ)
2018年4月12日 木曜日
始園式、入園式が終わり平成30年度新学期が始まりました。今日はその第1日目、年少年中、年長児が全員が揃いました。始園式の日に「年少さんが泣いていたら助けてあげてね。」と言われていた年中、年長児はバスの中から「年少さん大丈夫かな?」「部屋まで連れて行ってあげないかん。」と張り切っていました。
張り切っているのは教師も同じです。朝から新しく登園してくる子ども達をイメージしながら遊具を移動させたり、ままごとや砂泥遊びの準備をしたりしました。そして、時間になり次々登園してくる新入児達。教師が思っているよりも泣く子が少なく、カバンをかけたまま遊ぼうとする子もいました。その姿にこれからがとても楽しみになりました。
「お世話をしてあげなくちゃ!」と張り切っていたTちゃんは、同じバスの年少さんと手をつなぎ、部屋まで連れて行ってあげていました。…が、そうそう思うようにはいきません。部屋まで行く途中にある白鳥の乗り物にちょっぴり寄り道!!
「荷物を置いてから遊ぼう。」「シール貼りに行こう!」と誘うものの、ついには「先生―!なんとかして!!」と助けを求めてきました。その後、教師と一緒になんとか説得して、無事に部屋まで送り届けることができました。
その後もしっかり自己主張する年少さんは、早速自分の好きな遊びを見つけて楽しんでいました。年中、年長児は午前保育で遊び足りず「まだ遊びたーい。」と言いながらも進級してすぐの子ども達は「さすが年中さん!さすが年長さん!」と言われると胸をはって積極的に片づけをしてくれていました。
部屋に戻ってからは帽子に名前を書いていきました。「あーなたのおなまえは?」と聞くとニコニコしながら「〇〇 〇〇です」と名前を教えてくれました。そして、「頭を動かさないでね。」と言いながら一文字一文字書いていきました。「できた!」と言うと、一度帽子をぬいで確認し、指で押さえながら描かれた字を読んでいました。新しいクラスの子ども達と気持ちがぐっと近づいた活動になったように思います。まだ書けていない子どもには明日、心を込めて書きたいと思います。
そして、明日も笑顔で登園してもらえるように、楽しい環境を準備して子ども達を迎え入れたいと思います。
2015年2月21日 土曜日
今日はフリースクールとして学研幼児教室の指導員の方による護身教室を開催しました。いつものフリースクールより、卒園児の参加が多く、最近の子どもが巻き込まれた事件に関心が高いということを実感しました。
普段から月に1度以上の避難訓練を通し、身を守るために、自分たちがすべきこと、先生たちがすべきことを知っている子どもたちは副園長の話の中で「急に連れて行かれそうになったらどうする。」と手を引っ張られたT君は大きな声で「たすけてー!」と言うことができていました。そして、長期休みの前にいつも話してもらっている『イカのおすし』 『イカ』-いかない 『の』-のらない 『お』-おおごえで 『す』-すぐに 『し』-しらせる の話をしてもらいました。実は『イカのおすし』には踊りがあります。この歌はキラキラというグループが子どもを守るために作ったもので、楽しく踊りながら、自分の身を守る方法を覚えていきます。この歌でデビューしたキラキラさんは何度も三葉幼稚園にきて、子どもたちと一緒に歌って、踊って下さって、幼稚園児たちが松山市内での歌の普及に一役をになったいきさつがあります。
さて、護身教室では、まず、「やるときはやる」「話を聞くときは聞く」「楽しいことはしっかり楽しむ。」を約束し始まりました。そして教室では「礼で始まり礼で終わります。」と正座で姿勢を正し、「黙とう」と目を閉じ心を落ち着かせ、「礼」「おねがいします。」といつもとは違う雰囲気に子どもたちは真剣にそしてやる気いっぱいな表情をしていました。
今日、護身術で教えてもらったのは3つの技、3つの魔法の言葉です。
その1 片手で腕をつかまれた時は… 「へんしん!」
手をつかまれた瞬間、その手を「へんしん」と思い切りあごのあたりに振り払います。ここで重要なのは、手をひねりながらすることと、ひねる方向です。それができると、お父さんでも手を振り払うことができていました。
その2 両手で腕をつかまれた時は… 「うんとこしょ!」
両手で手をつかまれた時、反対の手でつかまれてしまった手を持ち「うんとこしょ!」と引き抜きます。大きなカブやいもほりのようにと言われると、上手に自分の手を引き抜くことができていました。
その3 胸をつかまれた時は… 「エイエイオー!」
両手で胸ぐらをつかまれた時は、つかまれた腕の間に「エイエイオー」と拳を高く上げると逃げることができていました。
そして、この3つの技には共通する大切なことがありました。技が成功して絵が離れたときは『イカのおすし!』すぐに反対方向に「たすけてー!」と大きな声を出しながら逃げなければいけません。今日は保護者と子どもでしたのですが、最後にインタビューされたお父さんは「今日は護身術で娘に本当に手を外されびっくりしました。」と話されていたのが印象的でした。
護身術を習った後、スポーツチャンバラを体験しました。
体の俊敏性を養うねらいがあります。」と説明されていたのが納得!打つ、よける、防ぐという動きをすることで筋力、洞察力、反射神経など様々なところが育つということを感じました。なんといってもスポーツチャンバラの時間はみんな目が本気!途中から保護者や教師も参加したのですが、大人までが本気になっていました。日頃のうっぷんを… とばかりにとても気持ち良さそうに叩いていました。
スポーツチャンバラでも「礼に始まり礼に終わる」といことで最後も「黙とう」と「礼」をして終わりました。
今回の教室で教わったことはフリースクールだけで終わらせず、保育の中にも取り入れていきたいと思います。
今日はいつもプレイルームでお世話になっている先生も指導員として参加してくださり、子どもたちも喜んでいました。楽しい時間を作って下さった先生方、ありがとうございました。
コメント (「護身教室がありました!」 ひつじ組 河野拓成 はコメントを受け付けていません)
2015年2月13日 金曜日
「おはよう!」と挨拶する声がどことなくいつもより明るく、自信に満ちた表情で登園してきた子ども達。「お母さんにかっこ良かったって言ってもらった。」「あんなにすごいと思ってなかった。って言ってた。」と発表会を褒めてもらったはなしをとびっきりの笑顔でしてくれました。
気分はまだ発表会の子ども達は自然とデッキの前に集まり「ソレソレソレソレ祭りだ祭りの曲かけて!」「きょうりゅうダンスが良い。」と踊りが始まりました。自分の曲がかかると自信を持って前に立ち、手本として力強く踊っていました。びっくりしたのは子ども達は、他の学年のクラスの踊りも、いつの間にか覚えているのです。ひよこ組や年少組は憧れの「ソレソレソレソレ祭りだ祭り」を踊ると、顔つきは真剣、目線までポンポンの先や指先を見て踊っていました。間奏の時の『足あげポーズ!』は頭をつけながら足を一生懸命あげる姿に思わず拍手をしてしまいました。
逆に、年少さんのオペレッタやきょうりゅうダンスに年中、年長も参加している姿がとてもかわいく、微笑ましく見えました。ひよこ組のオペレッタになると主役はやっぱりひよこ組さん。周り関係なく、自分の役をやりきっていました。楽しそうな声に誘われて、ぴよぴよ組までテラスに出てきて真似ながら踊っていました。
今日はとても暖かく、発表会の曲が心地よく聞こえてくる中、ほとんどの子ども達が戸外に出て遊んでいました。どの遊びもとてもいい雰囲気なのを感じ取ったのか、ひつじ組のA君は「今日は特別な日なん?すっごい楽しい。」と話し、「発表会をみんなが頑張ったけん特別な日やね。」と話が盛り上がりました。
駐車場の梅の花が咲き始めていることに気づいていた年長のK君が、枝が折れていることに気づき拾ってきて水に生けてみることにしました。K君は「毎日観察する。」と張り切っています。
また、桜の木につぼみができていることに気づいたり、チューリップの土が乾いているのに気づき、水をあげる姿もあしました。「桜やチューリップが咲くころには年長さんやね」と年長になることに期待を持っている子ども達にこれからも1日1日を大切に生活し、あと少しのひつじ組を楽しめるようにしていきたいと思います。
コメント (「楽しかった発表会!!」 ひつじ組 河野拓成 はコメントを受け付けていません)
2014年11月25日 火曜日
今日から待ちに待った自由参観日が始まりました。登園するバスの中でも「今日お母さん来てくれるんよ。」「私のお母さんは今日仕事やけん明日!。」と子ども達も楽しみにしていました。そして、自由参観日と同時に楽しみにしていたのが、年長組のみつばスーパーのオープンです。金曜日に下見に行った年少・年中児は「指輪があったよ。」「ゲームしたい。魚釣りが楽しそう。」と自分のほしいものしたいものが決まっていました。ひつじ組のH君は一通り下見をした後、「あっ!みつばスーパーも袋があったら値引きしてくれるんかな。」と思いだし聞きに行っていました。そして、「値引きしてくれるって。」とみんなに伝えると、それぞれがエコ袋やエコかごを準備し始めました。
準備万端の年少・年長児、オープンと同時に今日は、うさぎ組、りす組、ひまわり組、ちゅうりっぷ組、たんぽぽ組が買い物に行きました。買い物に行くと、年長組さんがお金を持ってきていない子は、銀行でお金をおろせることやおろし方を教えてくれました。今年初めてのやり取りでアクシデントも発生していました。
銀行では利用者が予想以上に多かったようでおろせるお金が無くなってしまいました。「少し待ってください。」と待ってもらいながら裏ではお金の製造が急ピッチで行われていました。
洋服屋さんでは「私に合う服あるかしら。」と難題を持ちかける教師にサイズを聞きながら製造販売する姿も見られました。
ゲーム屋さんでは、年少さんが楽しくなり、ゲームが進まず、担当の年長さんが頭を抱える事がありました。どうにかしなければいけないと考えたS君は「時間を決めよう!30秒ね。」とルールを追加していました。
レストランではお客さんがどんどん来て、商品がなくなると、自然と役割分担ができてきて、売る人、作る人、説明する人、と分かれ、時には「先生!足りんよっていうだけじゃなく手伝ってよ。」と教師が注意される一幕もありました。
保護者の方も沢山参加してくださり、子ども達が頭を使わなければならないような声を沢山かけて頂きました。三葉の保育、三葉のお店屋さんを理解してかかわってくださっていることを嬉しく思いました。今週末まで、お店屋さんんが深まるように盛り上げていきたいと思います。
また、ひつじ組は壁面作りをしました。先週、幼稚園を作ることを子ども達と話し合っていたので、すぐに「サッカーしてる所が良い。」「つりかん描く。」とそれぞれイメージし、絵を描いていきました。いろいろな所をよく見ている子ども達は、「砂場の木は真っ赤な葉っぱ。」「銀杏の木は黄色と緑と2つの色。」と葉の変化や違いにも気付いていました。「木登りしてる。」「かくれんぼ」と好きな遊びを楽しんでいるとっても楽しい壁面ができました。
コメント (「お店屋さんがオープンしました。」 ひつじ組 河野拓成 はコメントを受け付けていません)
2014年7月15日 火曜日
朝、バスが幼稚園に着くと、心地よい太鼓の音が聞こえてきました。「ソレ ソレ ソレ ソレ トトンのトン♪」とリズム良く、思わず運転手さんも「お!上手になってきたな。」と褒めてくれました。昨日、初めて自分のうちわを持って踊った子ども達。太鼓の音が聞こえると、「今日もうちわ持って踊れる?」「早く踊りたい。」とやる気十分でした。そして、いざ盆踊りの時間、気付けば年長児の中に頭に何かつけている子どもがいました。すると、子ども達が、「あっ!そら豆や!」「そら豆を頭につけとる。」と大騒ぎ。すぐに「僕たちも作りたい。」と言って来ました。早速、昼食を食べ終わった子ども達から空き箱を探して、そら豆のお面を作りが始まりました。一人ひとり違った色々な形のそら豆がいて、「そら豆の家族。」と言って沢山のそら豆を描いている子や、自分がそら豆になりきり「私がそら豆」と大きいそら豆を描く子、年少さんには川のままのそら豆を描いている子もいました。表情一つ見ても、同じ表情はなく、世界で一つのお面ができました。
今回の夕涼み会には年長児達で作詞、副園長作曲の三葉オリジナル曲「そら豆音頭」が登場し、また一層夕涼み会が楽しみになりました。
また今日は1学期最後の手作り給食がありました。最後ということでメニューはみんな大好きカレーライスでした。具も沢山入った具だくさんカレーをみんな 食べる食べる!お代わりを何度もする子もいました。そしてとても食べやすかったキュウリともやしの酢の物に運転手さんが育ててくれたとっても甘いトウモロコシもありました。みんな全部食べ大満足でした。
そして、ひつじ組は降園前年長のくじら組さんに出張紙芝居を見せてもらいました。約束する際、くじら組のA君が楽しい所をアピールしてくれたので、みんなとても楽しみに待っていました。そして、約束通りくじら組さんが来てくれて、自分たちで準備をする姿や、はきはき紙芝居を読む姿に憧れの気持ちを持って見ていました。終わった後に感想を言ったり、「私たちも作ってみたい。」と早く年長になることを楽しみにしていました。
少しずつ伝統となりつつある紙芝居作りで様々な学びがあり、お互いが刺激し合えていることを実感し、これからも大切にしていきたいと思っています。
コメント (「そら豆のお面を作ったよ!」 ひつじ組 河野拓成 はコメントを受け付けていません)
2014年4月14日 月曜日
「なんだかチューリップがお話ししてるみたい。」と年中児のAちゃんがとても嬉しそうにチューリップに話しかけていました。開いたチューリップを見ると、どのチューリップも朝日が昇る方に花を向けていました。手でチューリップの形を作って歌い始める子、中には話が広がってハチの話が弾んでいるグループもあり、様々な表現の仕方や興味の持ち方に驚かされました。 春の暖かさをいち早く感じ、今日は裸足になって遊ぶ子どもの姿も多く見られました。そして、「踊りしよう。エビカニクスかけて。」と元気いっぱい踊ったり、砂場でダイナミックに遊んだりしていました。新しいクラスにまだ慣れていない子も、年少の時の友達を見つけると一安心。たくさんの色の帽子がまじりあって遊んでいました。
今日は新しく、絵の具を使った浸し染めのコーナーを出していると、教師が作った浸し染めに色がたくさん混じっているのを見て、「ワァー!きれい!。あれやってみたい。」と何人もの子が興味を持って集まってきました。色と色がつながっていくまで我慢できず角々に別々の色がぶちのようになってしまい、「あれー?」と残念がっていた子が、何度かしていくうちに色が混じってしまい、今度は黒っぽい色になってしまっていました。これから毎日していく中で子ども達が色の変化やにじみ方など様々な事に気づき、色の不思議さや組み合わせによる違いなどを学習していく様子を楽しみにしながら、教師も共感したり、発見したりできるようにしていきたいと思います。
今日は今年度初めての給食がありました。朝から調理室からいい匂いがしてきて、何度も「先生、お腹すいた。」「早く給食食べたい。」と子ども達からせかされました。中には「古森先生が野菜採ってたよ。給食に入れてくれるんかな。」としっかり観察している子どももいました。そして、「いただきます。」と言うと、同時に「おいしー!」とたくさん食べ、用意されたお代わりの分のすぐになくなってしまいました。
職員紹介(年中組)
☆ ぱんだ組・りす組 ☆ ☆ ひつじ組・うさぎ組 ☆
うえだありさ・やまだみわ こうのひろなり・とみたみずほ
コメント (「チューリップが咲いたよ。」 ひつじ組 河野拓成 はコメントを受け付けていません)
2014年3月10日 月曜日
日差しを暖かく感じる中にも、春冷えと言われるシンシンと体の芯から冷えを感じる今朝も子ども達は登園して来ると戸外で元気一杯遊んでいました。チューリップを観察することが日課になっているAちゃん達は、「友達の分もあげよう。」と言って水やりをしていました。「だんだん伸びて来たね。」と言って嬉しそうに話し、草引きをしていました。球根を植える時に「年長さんになる頃に咲く」ということを聞いたことを覚えていて期待を持って世話をしていました。
しっぽ取りをしている子達は、遊んでいるうちに次第に人数が増えてきました。「Rくんは速いけんなかなか取れんのよ。」「2人でつかまえに行こうや。」などと友達と作戦を考えながら遊ぶ姿に成長を感じます。それを見た満3歳児のひよこ組のMくんは自分の帽子を背中に挟んでしっぽを作ると教師に「取って!」と言って逃げて行きました。教師が追いかけて取るとまた、しっぽを作って逃げて行きました。何度も何度も繰り返し教師が付き合っている間続くのが満3歳児なのです。このようにして小さい子達は年長児や年中児の生活や遊びを興味を持って見て真似て発達していきます。幼稚園の人間環境の影響は大きいのです。園生活を5年続けるぴよぴよさんは、もっともっと大きいと期待しています。
ひつじ組では、先週からシール帳折り紙の花の延長で春の壁面作りをしています。春のイメージを子ども達に聞くと、チューリップ・タンポポ・テントウムシ・チョウチョ・イチゴなどたくさんのものが挙がりました。自分の図鑑を見て描いたり、折り紙や包装紙を使って作ったりと色々な春の花や生き物で壁がいっぱいになりました。ウグイスを描きたいというNちゃんは自分の図鑑やお部屋の本を見たけれど、載っていなかったことを残念そうに話していました。今日違う図鑑のウグイスを教師が見せると時間をかけてパステルの色を少しずつ変えながら塗っていました。できあがった壁を見ると、自分が作ったものを友達に嬉しそうに説明する姿が見られました。お部屋がパッと春になって明るくなりました。帰りのバスでぞう組のAちゃんが窓の景色を見て「菜の花が咲いとる。もうすぐ春が来るんやね。」と話していました。自分が小さい時にこんなに自然のことに気付いていたかなと思い返しました。三葉での色々な経験が気付けるようになるんだろうなと感じました。
今日の給食のメニューは、具だくさん味噌汁、りんご、パンでした。味噌汁は大人気でおかわりもすぐになくなりました。年長児も三葉の味噌汁が最後なんだと残念に思いながらも、味わって食べていました。
コメント (「もうすぐ春が来るんだね。」 ひつじ組 立川留美 はコメントを受け付けていません)
















































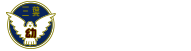

コメント (「みんなでいっぱい遊ぼうね!」 ひつじ組 河野拓成 はコメントを受け付けていません)