- blog
- album
- (089)-952-1777
- mituba@mituba.net
幼稚園の日記(ブログ)
2013年5月7日 火曜日
連休明けの今日、久しぶりに登園してきた子ども達は元気いっぱい「おはようございます!」と挨拶をして門をくぐってきました。
そろそろ園生活にも慣れてきた新入児達ですが、連休明けの今日はどんな表情で登園してくるのだろうかと、ちょっと心配していましたが、泣いて来た数名の子ども達も所持品の始末を終えると順に自分のしたい遊びへと向かっていました。
先週末から盛んになってきたスタンプコーナーは今日も年少から年長の子ども達で賑わっていました。 さくら組のIちゃんは細長い包装紙にスタンプを押して遊んでいましたが、しばらくしてそれを使ってこいのぼりを作ることにしました。押した形がうろこの模様になってプリンカップやペットボトルのキャップは目になりました。スタンプの乾いた紙を糊で貼り合わせて形にすると嬉しそうに吊るしました。
浸し染めの紙を使ったお花作りのコーナーでは年長児を中心に作ったお花を親子運動会のアーチに飾り付け素敵なアーチになりました。又、サッカーや遊具などで体を動かして思う存分好きな場所で汗をかきかき遊んだり、気温が上がってくると裸足になって砂場に水を運んで掘った穴や山に水を流して遊んだりする姿が見られるようになりました。乾いた園庭にホースで水をまくとキャーキャーと歓声が上がって水まきをする教師の側に子ども達が集まってきました。
色水コーナーでは連休中に見つけた花を幼稚園に持ってきてそれで色水を作っている年長の女の子達がいたり、浸し染めも紙の折り方を工夫して試したりして園での遊びに期待をもって登園してきている様子がうかがえ、教師達も一緒に楽しんでいます。
又、今日はカイワレ大根の種まきをする日でした。
連休前に副園長から「みんなはカイワレ大根のお母さんになってお世話してあげてね。」という話をしてもらったことを思いだした年中のS君は蒔いた種を見ながら「これから僕がカイワレさんのお母さんになってあげるんよ!」とつぶやいていました。年長児の女の子達は共同のケースに植えたカイワレの種がいくつあるか数えてみると156粒あったので「私156粒のカイワレ大根のお母さんにならんといかんのよ。」と意欲満々で話していました。
どのクラスでもカイワレ大根の種をとても慎重に又、大事そうに一粒一粒土の代わりの綿にまんべんなく蒔く姿が見られました。種まきが終わると土の中と同じ様に暗くして一週間くらい置くと芽が出てきてぐんぐん伸びていくのです。その様子を見るのがとても楽しみです。運動会当日までカイワレ大根の世話を一人ひとりが責任をもってできるよう援助していきたいと思います。
2011年6月2日 木曜日
梅雨に入り、いつ雨が降るのかと気にしていましたが、そんな心配のないほど今日は良い天気でした。園庭を歩いていると、 砂場では、年中児が砂場で温泉を作っていました。天気はとても良い一日でしたが、砂場の砂は少ししめっていて、冷んやりしていました。「ここはどうする?!」、「あれ?水がないぞ!」と次々会話が飛び交っています。 温泉の身体がつかるところ、水が流れる所、と区分けもしっかりできています。気がつくと出来上がった温泉には、可愛いお客さんがちょこんとはいっていました。
その隣では、さくら組のY君が大きなスコップを持って何かを作ろうとしていました。そして「先生もロケット作ろう!」と声をかけてくれました。。どうやら、砂でロケットを作ろうとしていたようでした。砂をどんどん積み上げてというY君からの指示で、山が出来ると、「次はこれを使うんだ!」と長いパイプを持ってきました。気が付けば仲間が増え、みんなで力を合わせパイプを差しました。そこからどんどん水を流すと砂も一緒に流れ、そこに穴があいていくのをしばらく楽しんでいましたが、Y君がさっきと同じくらいの長さのパイプを持って来て、さっき差したパイプの反対側に差し始めました。「見て見て!飛行機!」…離れて見てみると…「本当だ!飛行機だ!」…子どもの発想力には驚かされます。
砂場から園庭をみると、エンドレスリレー!色んな学年の子ども達が走っていました。走りたくてやって来た子ども達は二人で手を繋ぎしっかり並んでいます。「よーいどんしたい。」と言っていたさくら組のJちゃんはさくら組のお友達を自分から誘って、走って並んで、走って並んで、、満足するまで走っていました。
ひとしきりみんなが遊んで満足した頃、まんまるおんどの曲が流れ始めると、子ども達がどんどん集まってきました!今日はいつもに増して何重もの円が出来るほどでした。内側の円では大分踊れるようになった年少児たちが楽しそうに踊っていました。その周りでは年長児がしっかりと上手に踊っていました。私自身盆踊りは昨年が始めてだったので、今年は楽しんで子ども達と踊っていきたいなあと思います。
コメント (「園庭は今日もにぎやか」 さくら組 竹田佳那子 はコメントを受け付けていません)
2011年3月26日 土曜日
今日は平成16年度卒園生の「卒業おめでとう会」がありました。「卒業おめでとう会」とは、三葉幼稚園を卒園した小学6年生を幼稚園に招待して小学校卒業をお祝いするものです。今年は卒園生の約半分の62名が参加してくれました。
私にとっては、幼稚園に就職して1年目の卒園生ということもあり、例年よりも思いが深い子ども達でした。準備を進めていると、集合時間の1時間半前にもかかわらず、早速卒園生がやって来ました。幼稚園を卒園してからも仲の良かった男の子5人組です。久しぶりの幼稚園を喜び、遊具や砂場で遊ぶ様子は6年前の幼稚園児の姿に戻っていました。ほぼ全員が揃ったところで、園舎をバックに記念撮影をしました。三葉幼稚園を卒園して以来の集合写真は、どこか緊張している様子も伺えましたが、きっと卒園生達の良き思い出となる素敵な写真になったと思います。
副園長からの話では、「中学生は大人と子どもが半分半分の難しい時期。中学生になって悩み、つまづいても幼稚園に帰ってきていいんだよ。」と優しく声を掛けてもらいました。その後、一人ひとりが小学校で頑張ったことや、中学生になって頑張りたいことなどをまじえて、自己紹介をしていきました。幼稚園の頃は引っ込み思案でおとなしかった子、わんぱくで落ち着きのなかった子も、自分の声でしっかりと自分の思いを発言することができていて、立派に成長している姿に感心させられました。その中には「スポーツを頑張った!」「勉強とスポーツを両立していきたい!」「友達と仲良く過ごすことができた!」など、三葉幼稚園で伸び伸びと育ったみつばっ子らしい目標や感想が多くあり、とても嬉しく思いました。卒園生みんなでゲームを楽しんだ後は、先生達手作りのおやつの時間です。今日の献立は、「豆腐団子とさつまいものスイーツ」でした。三葉幼稚園の食育が始まる前の卒園生ということで、手作りをとても喜んで、会話を弾ませながら楽しい雰囲気の中でいただくことができました。
始めに撮った記念写真のプレゼントをもらった後、副園長から大切な話がありました。「震災に遭われた方は、1つの物を分け合って食べたり、譲り合って体を休めたりしている。また、事故や病気などで亡くなった方もいる。今、こうして出会えたこと、生きているということに感謝して、命を大切にし支え合っていって欲しい。」これは私たち教師も同じ願いなのです。三葉幼稚園を卒園した子ども達には、人を大切にし自分も大切にする心が育まれていると思います。もし、道に迷うことがあれば助けになり、これからも卒園生達の心の拠り所でありたいと思います。
コメント (「卒園生おかえり!」 さくら組 丸山利夫 はコメントを受け付けていません)
2011年2月9日 水曜日
先日、カラカラに乾いたチューリップのプランターを見て、副園長が「チューリップさん、喉が乾いてるんじゃないかな。」とつぶやきました。それを聞いた年少児達は、子ども用のジョロやままごとのお鍋やコップに水をついで、水やりを始めました。その頃からチューリップに関心を持つようになったさくら組のAくんが、今日はプランターに生えた雑草を抜いていました。「これは雑草っていうんよ。抜かないかんのよ。」と友達に教えてあげながら抜いていると、「あれ?この前よりも大きくなっとる!」とチューリップが生長していることに気付いたのでした。寒い季節の間でも少しずつ大きくなっているチューリップの生長を感じ取っている子どもの感性には感心させられます。水をあげることすら忘れてしまっていた私は反省させられたのでした。子ども達はひっそりと園庭の陽で生長し続ける植物や木々の変化をにも気付き、いつの間にかかかわっているのです。環境の大切さを改めて感じました。
生活発表会本番を迎えるに当たって、私は心配していることがありました。それは、先日の市民会館でのリハーサルのことです。「みんなで力を合わせて頑張ろう!」を目標に、年少のオペレッタの練習をしてきました。ところが、リハーサルでは、それぞれの子ども達が気の向くままに動いていて、気が乗らず、みんなが1つにまとまらなかったのです。私一人の力では、残り3日で集中させることは難しいのではないかと不安になり、職員会で話したところ、副園長をはじめ、たくさんの教師達が練習に協力してくれることになりました。そして、、昨日の練習で子ども達の姿も大きく変わっていったのでした。それは、子ども達の気持ちが盛り上がるような楽しい練習方法であったり、子ども達が理解し易い言葉掛けであったり、私のやり方とは違う方法でした。三葉幼稚園の良さは、一人の教師だけではなく、全員の教師が協力し合って保育をすることにあります。副園長から、「もうすぐ、年中組さんになるよね。大きい組さんになるには、みんなで一緒に力を合わせて頑張るんだよ。」と話してもらい、子ども達からは元気よく、「はい!」と返事が返ってきました。今日は、カブの葉っぱの縄の持ち方についてアドバイスをしてもらい、持ち方を変えてみると子ども達の動きが揃ってきたのです。
練習後、「子ども達は縄を引っ張ったことがあるのかな?」と考えた私は、オペレッタの子ども達を誘って、綱引きをしてみることにしました。「持ち方はどうすればよかったかな?みんなで力を合わせて引っ張るんよ!」と声を掛け、きょうりゅうサンバチーム対大きなカブチームの綱引きが始まりました。大きなカブに出る子ども達は元気よく声を出して、「うんとこしょ!どっこいしょ!」と力を合わせて綱を引っ張り、見事きょうりゅうサンバチームに勝ったのでした。
生活発表会は、幼稚園の生活を発表する学年の締めくくりの行事です。きっと年少のオペレッタの子ども達も本番では、みんなと一緒に、元気いっぱい、笑顔で演技してくれることだと思います。みんなの先生達や年長児たちの温かい励ましや応援をもらって成長する子ども達は、年中になった時、今度は自分達が小さいお友達を励ましたり、応援したり、温かい心配りを見せるようになるのだと思います。
コメント (「大きい組さんになるためには・・・。」 さくら組 丸山利夫 はコメントを受け付けていません)
2011年1月18日 火曜日
今日のさくら組の保育予定は、子ども達とオペレッタのお面を作ることでした。子ども達の目に付くように、テラスに用意していると登園してきたYちゃんが、「先生、何しよん?」と近づいてきました。「Yちゃんはオペレッタの娘さん役よね?何か作る?」と声を掛けると、早速包装紙や廃材を使って、娘さんの髪飾りを作り始めました。その姿を見て、たんぽぽ組のMちゃんやひまわり組のRちゃんもやってきて、一緒に作り始めました。発表会に向けて練習を進めていく中で、子ども達の発想を大切にしながら、意欲を持って取り組めるように、今後も援助していきたいと思います。
今日も三葉幼稚園の園庭は、元気いっぱいの三葉っ子達の姿で溢れていました。そんな子ども達の様子を見た副園長のアドバイスから、赤コースの年中・年少児は、屋外遊ぎ場に出掛けることにしました。屋外遊ぎ場では、凧揚げやクラス対抗凧リレーをしたり、新しく色を塗り直して整備された遊具を使って遊んだりしました。いつもなら、園庭の中を友達とぶつからないように気をつけながら走っていた子ども達も、屋外遊ぎ場では伸び伸びと思いっきり走る姿が見られ、ほっぺを真っ赤にしながら笑顔いっぱいでした。また、屋外遊ぎ場は障害物がないので風の通りがよく、走らなくても凧が自然と風にのって飛んでいました。自分達が走らなくても凧が揚がることに気付いた子ども達は、風の力を意識してきたようでした。明日は、天候が良ければ青コースの年中・年少児が出掛ける予定になっています。私は、風の力だけでどれ位まで凧が揚がるのかを子ども達と一緒に試してみたいと思います。
今日は、こあら組の子ども達の初めての一人登園でした。泣いて来るかなと心配していましたが、ほとんどのこあら組の子ども達が、泣くことなく登園することができました。また、戸外に出て在園児に混じって、ままごとや砂遊びを楽しんだり、ウサギにえさをあげたりして、自分のしたい遊びを見つけて楽しんでいました。今日は、青コースの年長児が、こあら組の降園のお手伝いをしました。一緒に靴を探したり、手をつないでバスの乗り場まで連れて行ったり、優しく接する姿が見られ、とても微笑ましい光景でした。明日もこあら組の子ども達が安心して楽しく過ごすことができるように環境を整え、迎えてあげたいと思います。
今日は、保育所ぴよぴよ組の手作り給食の日でした。
メニューは、「オムライス・サツマイモのスティックフライ・キャベツと鶏肉のスープ・リンゴ・園内で採れたブロッコリー」でした。ぴよぴよ組の子ども達は、お腹いっぱいおいしく頂きました。
コメント (「こあら組さん、ドキドキの一人登園!!」 さくら組 丸山利夫 はコメントを受け付けていません)
2010年12月6日 月曜日
今朝、バスで子ども達を迎えに行くと、保護者の方が「先生、あれ見てください。」と家の方を指差しました。その方向を見ると、フリースクールで作った干し柿が軒下に吊るされていたのでした。「今から、食べれるようになるのが楽しみです。」という、保護者の方の笑顔を見て、とても嬉しくなりました。幼稚園に着くと、テントの所に年長児が集まり、何やら話をしていました。覗いてみると、干し芋と干し大根を囲んで、フリースクールに来ていなかった友達に、ぞう組のTくんが、「太陽パワーをもらって栄養いっぱいにしよるんよ!」と得意げに話していました。フリースクールで学んだことを、分かるように説明しているTくんの姿を見て、さすが三葉幼稚園の年長児だなと感心しました。朝は冷え込むため、包丁ままごとのコーナーには、風を防ぐシートを張りました。冬の訪れもそんなに遠くないこの時期は、寒さが突然やって来ます。寒さを防ぎながら楽しく遊ぶためには、どのように工夫していけば良いか考えたり、先人の生活の知恵を知ったりしながら、子ども達には生きていく知恵を身に付けていって欲しいと思います。
さくら組では、最近「戸外で体を動かして遊ぼう!」を合言葉に、外でサッカーをしたり、縄跳びをしたりして遊んでいます。先週からは登り棒に挑戦する子ども達の姿が見られるようになりました。そして、驚くことにさくら組のKくんは、手と足を器用に使って、登り棒の頂上まで登ることができるようになっていました。これには、周りにいた子ども達から拍手が起こり、Kくんは少し照れくさそうにしながらも嬉しそうでした。今、年少児は年中・年長児の姿に憧れを持ち、色々な遊びをしています。つりかん、鉄棒など年少児一人の力では難しい遊具には、教師が援助しながら、子ども達が満足感や達成感が味わえるようにしていきたいと思います。
また、今日は11月以降に入園してきたひよこ組の子ども達と駐車場の畑に植えているさつまいもを掘りに行きました。満3歳児が教師の話しをしっかりと聞いて、さつまいもが折れないように丁寧に掘る姿に、ここでも感心させられました。掘っている途中、幼稚園の近くを通るJRの踏み切りの音が鳴り出すと、「電車が来る!」というYくんの声を合図に、ひよこ組全員が一列に並んで、電車が通るのを眺めていました。私は、ひよこ組が素早く反応し、同じような行動をする姿がとても新鮮で面白く感じました。何にでも興味や関心を示し、ちょっとした変化にも反応する、満3歳児の感性の豊かさに驚かされたのでした。
「みんなで玉ねぎを植えたよ!」 年中組
例年は、年長児が行っていた玉ねぎの苗植えに、今年度は来年度、年長組になる年中児が植えに行きました。副園長から、玉ねぎの苗は種から育てたことを聞き、子ども達は「へぇー」「すごい!」と驚いていました。教師達の中にも、初めて見た者もいて、感心して聞いていました。「苗をお日様が出てくる方に向けて、寝かせて植えるよ。」と副園長に教えてもらい、子ども達は1本1本丁寧に植えていきました。今後も、来年収穫することを楽しみにしながら観察したり、水やりをしたりしたいと思います。
また、農園にはびわの木やいちじくの木もあります。そのびわの木は、たくさんの花が咲いていました。副園長から「びわの花にたくさんの蜂が来ているよ。みんな、お化粧をして次の花の所に行っているね。」と話してもらうと、「うわー!みんながお引越しをしてる!!」とWちゃんが声をあげました。ミツバチだけでなく、小さな蜂からチョウチョまで集まり、大盛況のびわの木でした。そして、いちじくの木は、大きなグローブのような葉っぱが黄色く色付き、地面にポロポロと落ちていました。その葉っぱを副園長が1枚持って、子ども達の所へやって来ると、それを見たMくんは「その葉っぱに目を開けたらいいね!」と言いました。それを聞いた副園長は、たくさんのいちじくの葉っぱを採って、袋に入れてくれました。帰ってから、そのいちじくの葉っぱはお面や扇子に、びわの葉っぱはロバの耳にして遊ぶ姿が見られました。子ども達の発想力や表現力の素晴らしさには、感動するばかりです。ただでは帰らぬ、三葉っ子達はたくさん学び、吸収しながら成長しています。
コメント (「体を動かして遊ぼう!&玉ねぎを植えたよ!」さくら組 丸山利夫 はコメントを受け付けていません)
2010年11月11日 木曜日
今朝、バスのお迎えから帰ってくると、さくら組のテラスに渋柿が吊るされていました。それを興味津々に見ていたさくら組のKくんは、「先生!これ柿でしょ?どうするの?」と聞いてきました。「今から干すんよ。干して太陽のパワーをもらったら、甘くなって食べれるようになるけんね。待っててね。」と答えるとにっこりと笑って、吊るしている柿を嬉しそうに見ていました。ボールの中を覗くと、皮をむいた渋柿がまだ残っていたので近くにいたぞう組の子ども達を誘って吊るすことにしました。見本で教師が吊るしていた柿を見て、「縄がいるよ!」と気づいたRくんは、傍にあるわらのコーナーに行って縄をなって持って来ました。次に、柿を縄に吊るそうとしましたが、どうやって吊るせば良いのかが分からず、困っていました。すると、横にいたKくんが、「先生が作ったやつを見てみよう!」と言って、教師の吊るしてている柿をじっと観察し始めました。そして、「わかった!縄の間に木を通せば良いんよ!」と気づきました。そして、見事に柿を吊るすことができたKくんに、周りにいた子ども達からは拍手が起こりました。改めて5歳児の観察する力には驚かされたのでした。観察をして、どんな仕組みで柿が縄に吊るされているのかを理解し、教師の見本と同じように作ることができたKくんは、さすが三葉幼稚園の年長児だなと感心しました。また、年中のYちゃんは、「年少さんの時は、お芋や大根も干しとったよね!」と、去年のことを思い出していました。「今度はYも、柿作りたいな!」と干し柿、干し芋、切り干し大根作りに期待をもっていました。また今年も干し柿や干し芋作りを通して、子ども達の心に残る体験ができれば良いなと思います。
明日は子ども達が待ちに待った遠足の日です。遠足に行く前に、年少の青コースのたんぽぽ組、ちゅうりっぷ組、さくら組が集まって、みんなで動物の鳴き声を聞くことができる大型絵本を見ることにしました。最初に出てきた動物は、ライオンでした。「ライオンの鳴き声ってどんな鳴き声かな?」という教師の質問に対して、子ども達からは「ガオーッ!!!」という元気な答が返ってきました。本の鳴き声も子ども達の予想通りに聞こえましたが、本物のライオンの迫力のある声に少し驚いた様子でした。その後は、ゾウやシマウマ、ゴリラなど聞き覚えのある動物達の声を聞いて楽しんでいきました。しかし、キリンの鳴き声は・・・・子ども達はキリンの名前は知っていても、鳴き声までは聞いたことがなかったようで、どんな鳴き声なのか想像できなかったようです。絵本の声を聞いてみると、「モー。モー。」という声で、子ども達は「ウシみたい!」と言って予想外の鳴き声に大笑いしていました。
最後に、遠足に行く時の約束事を話しました。一人で勝手に行動しないこと 先生の話をしっかりと聞くこと 周りの人の迷惑になることはしないことを約束して降園しました。運動会でお友達と並ぶことを覚え、園外保育などで歩くことに慣れてきた年少児は、きっと明日の遠足でもしっかりと約束を守って歩くことができるでしょう。
コメント (「遠足楽しみだね!」 さくら組 丸山利夫 はコメントを受け付けていません)









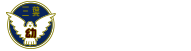

コメント (「カイワレ大根の種をまいたよ!」 さくら組 日野美雪 はコメントを受け付けていません)