- blog
- album
- (089)-952-1777
- mituba@mituba.net
幼稚園の日記(ブログ)
2013年3月19日 火曜日
『春が来た♪春が来た♪どこに来た♪』 以前のブログですみれ組のお部屋の桜が咲いていましたが、三葉幼稚園の園庭の桜の木もつぼみを大きく膨らませて春が来るのを待っています。桜の花よりも少し早く、年少児が植えたチューリップが大きく花を咲かせました。先週末から、少し赤く色付いたチューリップのつぼみを見て、「もう、花が咲きそうやね!」「絶対、赤色の花が咲くよ!」と花が開くことを楽しみにしていたひまわり組のCちゃんとYちゃんは、登園して来るときれいに咲いているチューリップをみつけました。「かわいい!」「チューリップが咲いとるよ!」と喜んでいました。三葉幼稚園の園庭にも、春はもうすぐそこまで来ていて、チューリップの花がそれを知らせてくれました。
今日は、在園児の3学期の終園式がありました。副園長から、「春休みは大きい組になる準備をする時だよ。自分のことは自分ですること。交通事故や踏切の事故には気を付けてね。」と話してもらうと、進級することに気を引き締めているようでした。来年度、兄弟が入園してくる子ども達は、みんなの前でお祝いの言葉や園歌、踊りを披露しました。どの子も自信をもって、元気よくお祝いの言葉を言うことができていて、威勢の良い踊りは頼もしさを感じさせました。「桜の花がたくさん咲いた頃には、みんな大きい組さんだね。」という副園長の言葉に、進級し新しい友達を迎えることに期待をもっている子ども達でした。
又、今日はクラス別のお別れ会と新クラスの発表もありました。お別れ会では、クラスの役員さんが考えてくれたゲームをしたりや歌を歌ったりして、教師や子ども達、参加した保護者も楽しんでいました。昼食は、副園長の手作りのカレーです。今日は、なんと700人分のカレーを作ってくれました。たくさんのカレーを、大人数でワイワイ食べながら、とても楽しい時間を過ごすことができました。
新クラスの発表では、新しい色の帽子を教師に被らせてもらって、とても嬉しそうな子ども達でした。春休みを挟んで、またひと回り成長した子ども達に会えるのが楽しみです。
2013年2月27日 水曜日
「先生!見に来て!」とひよこ組のRくんに手を引かれてついて行くと、そこには大きな雛人形がありました。会議室から1階のフロアに移動してきたことで、たくさんの子ども達の目に触れるようになったようで、今朝は登園してきた子ども達が雛人形の前に座って歌を歌ったり眺めたりしていました。
月曜日にひまわり組のSくんが、雛人形を見て気づいて質問してきた『靴を履いていない3人の男のお雛様』は、その後教師が調べたところ『足軽』(衛士とも呼ばれる)という人形であることがわかりました。お内裏様の傘や履物を運ぶ仕事をする人だということを伝えると、雛人形についてまた1つ知っていることが増えたことを喜んでいました。
先週末にひまわり組では、紙芝居作りが始まっていました。Sくんが絵を描いた紙をセロハンテープでつないでいたことがきっかけで、女の子達が興味を持ってひまわり組全体に広がってきたのでした。今日も紙芝居作りは続いていて、NちゃんとKちゃんが協力して作っていたのは、生活発表会で演じた「うらしまたろうの大冒険」のお話でした。そこに、仲良しの友達を登場させて、自分達でお話をアレンジしていました。そのお話をひまわり組の子ども達の前で読むと、みんなは興味津々で聞いていました。また、参観に来られていた保護者の方からも拍手をもらって、NちゃんとKちゃんはとても満足そうな表情でした。生活発表会で演じたうらしまたろうの話は、演じるという枠を越えて紙芝居の絵に表現されたり、話を創造したりと広がりがみられて、子ども達の表現力や創造力に驚かされました。
今日は、青コースの年中・年少・プレ年少のミニ発表会を行いました。発表会当日に欠席された方を対象に行いましたが、たくさんの保護者の方に参観して頂きました。子ども達は、元気いっぱい踊ったり手を伸ばすことを意識したりして伸び伸びと表現することができていました。しかし、私達教師の反省として欠席者の方、参観にこられた方をお招きする態勢が十分にできていなかったと思います。また、来年度は欠席された方も本番と同様に楽しんで頂けるように工夫が必要だと反省した教師達でした。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
本日より生活発表会の写真を展示しております。青コースはホール、赤コースは会議室に展示していますので参観に来られた方は、是非ご覧になって下さい。尚、駐車場が大変混み合っています。本日も詰め込みになっていて、お帰りの方から出られないと電話が掛かってきて、保育中にもかかわらず園側が対応に追われる状況がありました。職員達は保育中は体が空きませんので、早くお帰りになる方は、自転車や公共機関を利用されますようお願い致します。
コメント (「素敵な紙芝居作り&ミニ発表会」 ひまわり組 丸山利夫 はコメントを受け付けていません)
2013年2月1日 金曜日
2月3日は節分の日。今日は、4日の園内の豆まきに向けて子ども達と鬼のお面や豆作りをしました。4月の入園から廃材に親しんできた年少児達も秋の作品展を経験して発想力も豊かになってきました。パステルで鬼の絵を描いている子。ヤクルトのカップを鬼の角に見立てて廃材をくっつけて鬼の顔を作っている子。子ども達の素敵な発想がたくさん見られました。ちゅうりっぷ組のMくんは、廃材の中から紙のクッション(紙を細かく切ったもの)を探してくると、「鬼の髪の毛やぁー!」と言ってパステルで描いた鬼の顔にくっつけていました。他にも様々な廃材を工夫して使って楽しいお面が出来上がりました。三葉幼稚園の豆まきでは、同じお面は1つもなく、どれも個性的なお面ばかりです。月曜日の豆まきでは、どんなお面に出会えるのかとても楽しみです。






今日は2月17日に行われる生活発表会の案内状を持ち帰りました。三葉幼稚園では、「秋の運動会」「秋の作品展」「生活発表会」の3つの行事の案内状を、全て教師達の手で作っています。今から25年前の話です。三葉幼稚園に赴任してきた副園長は、一人で子ども達のために手作りの案内状を作り始めました。それは、「子ども達の後押しをしたい。子ども達に心を届けたい。」という思いからだそうです。その思いに感銘を受けた教師達は、副園長を手伝うようになり、いつしか手作りの案内状は三葉幼稚園の名物になっていました。今回の案内状は、年長児の劇がテーマになっています。初めて発表会の案内状を目にした年少児達は、「これは年長さんの劇やろ!」「このお菓子の家はヘンゼルとグレーテルのお話!」とイメージを膨らませながら嬉しそうに案内状を眺めていました。教師の手作りであることを伝えると、「お外が真っ暗になるまで作ってくれたんやろ?先生、ありがとう!」とお礼を言いに行く子どもの姿も見られました。自分達がくじを引いた座席のページでは、「僕は11を引いたけん、ここの席!お母さんはここに座るんよ!」と発表会を見に来てもらうことを楽しみにしている様子でした。手作りの案内状は、「創造・情緒・社会性」などたくさんの要素が含まれた総合的な教材なのだと驚かされました。今回の案内状が、生活発表会に向けて子ども達の気持ちを盛り上げる後押しになってくれれば嬉しいなと思います。


昨日から子ども達が楽しみにしていた手作り給食の献立は、「豚丼・キャベツ、きゅうり、大根とソーセージのサラダ・人参とかぼちゃのおやき・パイナップル」でした。今日のサラダは、副園長が味付けをしたのですが、いつもと違う味の変化に年長児は気づいていたようでした。豚丼の甘さとサラダの塩気が抜群にマッチしたおいしい昼食でした。

コメント (「楽しいお面ができたよ!」 ひまわり組 丸山利夫 はコメントを受け付けていません)
2012年12月20日 木曜日
『もうーいーくつ寝るとーお正月ー♪』子ども達がお正月の歌を口ずさんでいました。今年も残りわずかとなりました。三葉幼稚園では、今日2学期の終園式を行いました。
全園児がホールに集まると、年長児を手本に「小さい秋」の手話をみんなでしました。年少・年中児は、年長児から手話を教わる機会があるので完全ではありませんが覚えていて、年長児を見て上手に手話をすることができていました。私は覚えているつもりでも1つ1つをしっかりと理解できていなくて戸惑うところもあったのですが、年長児は1つ1つの意味を理解して感情も込めて表現することができていて感動させられました。副園長から、子ども達に対してこんな質問がありました。「小さい秋はぶどうや柿が実り、果物がおいしくなり、そして木の葉はまだまだ緑色だよね。じゃあ、大きい秋は何かな?」この質問に私は答えに困りました。しばらくすると、年中組の方から、「葉っぱが赤くなる!」と元気よく答えが返ってきました。「そうだね!大きい秋は葉っぱが真っ赤になったり、イチョウの葉が真っ黄色になったりするよね!」と副園長。小さい秋の歌からイメージを膨らませて、大きい秋を連想することができる子ども達の感情の豊かさに驚かされました。冬休みの過ごし方の約束を副園長と交わした子ども達は、『早寝早起きをすること・知らない人にはついていかないこと・怪我や病気をしないこと』など、しっかりと心に留めることができたと思います。
ひまわり組では、新年を迎えるにあたって、自分達の身の回りの片づけをしました。「今までいっぱい遊んだお部屋やけど、このままでいいんかな?」と子ども達に聞くと、「掃除せんといかん!」と気づいたようでした。そして、お道具箱の中身を整理したり室内のおもちゃをきれいに洗ったりしました。「お家の大掃除の手伝いもしてあげてね!」と言うと、「はーい!!」と元気いっぱいの返事が返ってきました。
そして、降園前には昨日のお昼に食べきれなかった干し柿をみんなで食べました。「おいしーね!」「甘いねー!」と言葉を交わす子ども達に、「何で干すと柿は甘くなったんかな?」と聞いてみました。すると、ZくんとNちゃんが「太陽パワーで甘くなったんよ!」「栄養がいっぱいになるって古森先生が言いよったよ!」と言いました。以前に副園長から聞いた話の内容をしっかりと理解して覚えていたことをとても嬉しく思いました。
2学期は運動会、作品展、遠足などなどたくさんの行事を通して様々な体験をしてきた子ども達からは、感情や創造性の豊かさが感じられました。3学期も、子ども達が楽しんだり考えたりしながら、心豊かな園生活が送れるように努めていきたいと思います。
コメント (「2学期が終わったよ!」 ひまわり組 丸山利夫 はコメントを受け付けていません)
2012年11月29日 木曜日
昨日、年中のお兄ちゃんお姉ちゃんに焼き芋を分けてもらったひまわり組の子ども達は、早速家から新聞紙とアルミホイルを持ってきました。「先生!新聞とアルミホイル持ってきたよ!」「早く焼き芋作ろう!」と、焼き芋作りをとても楽しみにしていました。 今回の焼き芋では、「自分の物は、自分で用意しよう」ということで新聞紙やアルミホイルは、自分で用意した物を使っています。今日は、各クラスで色々なエピソードがありました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ひよこ組のKちゃんは、焼き芋に新聞紙とアルミホイルがいることをお母さんに伝えて、用意した新聞紙とアルミホイルをしっかりと握って幼稚園まで持ってきました。
ぱんだ組のAちゃんは、昨日友達がアルミホイルを持ってきていなかったことを心配して、今日、もう1本アルミホイルを持ってきたのでした。お母さんから、「これ以上持っていくとお家のご飯が作れなくなるよ。」と言われたようです。
すみれ組のSちゃんは、友達のAくんがアルミホイルを持っていなかったことで、焼き芋を食べられないと心配して泣いてしまいました。そして、自分のアルミホイルをAくんに分けてあげて一緒に焼き芋を作ったのでした。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
このようにたくさんのエピソードがありました。「必要な物は自分で用意すること」当たり前のことのようですが、子ども達には経験させていなかったのではないかと反省した教師達でした。
さあ、いよいよ焼き芋作りの開始です!きれいに洗ったさつま芋を水でぬらした新聞紙で包みます。新聞紙がしっかりとぬれていないと新聞紙がアルミホイルの内側で燃えてしまい、さつま芋が焦げてきれいに焼けないのです。次に、新聞紙で包んださつま芋をアルミホイルで包みます。アルミホイルを巻くときに隙間ができてしまうと、そこから火が入ってしまい、これも焦げる原因になります。子ども達は、アルミホイルが破れないように慎重に巻いていました。子ども達がくるんださつま芋を受け取った教師は、「おいしく焼くからね!楽しみにしていてね!」と言って焚き火の中に入れました。おいしい焼き芋を作るには、焦げないように火の加減や焼き時間に気をつけなければいけませんが、子ども達が新聞紙やアルミホイルを巻く行程も、とても大切なのです。おいしい焼き芋作りのなかにも科学的な要素がたくさん詰まっていました。焼き芋作りを通して、子ども達はまた1つ新しい科学を勉強することができました。焼き芋作りという活動1つをとって見ても、子ども達の学びはたくさんあるのだと改めて感じました。
今日は、ぱんだ組とうさぎ組が干し柿づくりをしていました。うさぎ組では、柿以外にしいたけと大根も干していました。太陽に当てて乾燥させることで、甘味や栄養価が増す話をすると、子ども達は興味津々で聞いていました。今年は、園児数分の干し柿が2階のテラスに干されています。今年は例年以上に2階の軒下がにぎわっています。
くじら組と宮前校区の子ども達は、宮前フェスティバルに参加しました。小学校の先生やお兄さん、お姉さんの話を静かに聞いて大変頼もしかったようです。フェスティバルでは、ゲームや作るコーナーを楽しみました。作った物やもらったプレゼントをお土産として大切に持ち帰り、楽しい思い出ができました。
コメント (「焼き芋のなかにも科学がいっぱい!」 ひまわり組 丸山利夫 はコメントを受け付けていません)
2012年11月6日 火曜日
10月末に収穫して稲木に干していた稲から、もみを副園長が採っていました。今までもみを割り箸や木材で採る方法をやっていましたが、1番効率よく採る方法は指で採る方法でした。力加減が分かると一粒ももみが残ることなくきれいに採ることができたのです。この方法には若い教師たちも驚いた様子でした。稲からもみを採るとわらが出来上がります。今日は、わらを使って縄をなうコーナーを出すことになりました。そうこうしていると子どもたちが登園してきました。「先生、おはよう!何しよん?」と興味津々の子どもたち。子どもたちの視線の先には、縄をない終えて、その縄からわらぞうりを作っている副園長の姿がありました。わらぞうり作りは、日本の文化です。三葉幼稚園では、こうした昔から伝わる伝統ある文化を遊びのなかに取り入れています。副園長が作り終えたぞうりを子どもたちは順番に履いて、「気持ちいい!」「作りたい!」と気持ちが盛り上がっていました。くま組のYちゃんは、副園長の姿を見ながらぞうり作りを始めました。わらから縄をなって、できた縄をリボンの形にしてわらを編み込んでいきます。分からないところは教師に聞きながら、時間をかけて作っていきました。鼻緒の部分は、教師も分からなかったので副園長に教えてもらって、最後に鼻緒に布を巻いて完成させました。「もう1つ作ったら、作品展に出せるね!」とYちゃんはぞうりの片方を作ることにやる気を燃やしていました。作品展には、Yちゃんのように一生懸命に作った作品が出品されます。今年はどんな素敵な作品ができるのか楽しみです。
作品づくりが盛り上がっているなか、くじら組ではあることが・・・。「ピタゴラゆうえんち」が楽しくて楽しくて仕方がないくじら組の子どもたちは、作品づくりがなかなか進んでいないのでした。それを聞いた副園長はくじら組の子どもたちに、「やるべきことをやってから、また作ればいいじゃない。」と声を掛け、三葉幼稚園の建物の模型を見せてくれました。幼稚園の設計ができた時に建築士さんが造って下さった本物の縮小模型です。幼稚園の模型を見て刺激を受けたくじら組の子どもたちは、作品を作るイメージが湧いて意欲が高まったようでした。
ひまわり組では、先週こんなことがありました。風が冷たくて気温が下がった日のことです。寒いということから、子どもたちは雪をイメージしたようで、「雪合戦がしたい!」と言い出したのです。廃材を細かくはさみで切って雪を作ると、それを上からパラパラと降らせて遊んでいました。しかし、はさみで切るのには時間がかかります。そこで、新聞紙を手で破ってみることを提案してみると、子どもたちは喜んで新聞紙を破り始めました。新聞紙の雪で体がもぐってしまう程の量になったことで、Sくんが「このなか温かい!お風呂みたいや!」と言ったのです。それを聞いた他の子どもたちも、その中に入ってお風呂ごっこが始まりました。今日は、去年の廃棄になったバザーの券を出していたことで、チケットのやり取りをしてお風呂屋さんごっこをしていました。年長・年中児から、たくさんの刺激を受けて遊びを広げているひまわり組の子どもたちの育ちが感じられ、とても嬉しくなりました。
明日は、青コースの乗馬があります。乗馬に向けて、馬が出てくる絵本を読んだり馬に乗る練習をしたりしました。馬に乗る時の約束をしっかりと覚えて、明日の乗馬に期待を持って降園した子どもたちでした。
コメント (「たくさんの刺激のなかで」 ひまわり組 丸山利夫 はコメントを受け付けていません)
2012年10月11日 木曜日
今朝は少し肌寒く感じるなか、子どもたちが元気いっぱい登園して来ました。門で子どもたちを迎えると、「おはよう!今日は寒いね。」と少し足早に保育室へと入っていきました。そんななか、早く登園していたたんぽぽ組のRくんとちゅうりっぷ組のSくんがブランコをしながらこんな会話をしていました。
Sくん 「寒いけん、秋やね。秋の次は冬がくるんよ。」
「なんで知ってるの?」と副園長。
Sくん 「おじいちゃんが教えてくれたんよ。」
Rくん 「そうなん。それじゃ、秋やけん、雪遊びしよう!」
Sくん 「秋は雪遊びできんよ。雪遊びは冬よ!」
二人はこんな会話を交わしていたのでした。おじいちゃんが孫のSくんに掛けたであろう季節の移り変わりの話をSくんはきちんと理解していて、今朝のちょっぴり感じる肌寒さと結び付けていたようです。子どもたちにとって、おじいちゃんの存在というものが大きいということに気づかされました。
今日は、先週の「流しそうめん」の遊びから、さらに新しい遊びが砂場で行われていました。副園長が以前使っていた流しそうめん用の竹を持って来て、子どもたちが使いやすい長さに切ってくれました。それをみつけた年長児たちは、早速といをつないで遊び始めました。といのつなぎ目を高くするために、竹や木材を使っていましたが、たくさん遊び込んだ経験のあるくじら組のNくんは、身近にあるキャリーや鍋、椅子を運んできて、ちょうど良い高さにつなぎ目を置くことができていました。そんな様子を近くで見ていた年少児たちも、仲間に入れてもらって水を流したり、「ちょっと持っていて。」と年長児からお手伝いを頼まれて、しっかりと役割をこなしたりしていました。そのなかで、すみれ組のKくんは、といのつなぎ目から水が漏れていることが気になって、その部分に小さな板を差し込みました。すると、水漏れはしなくなって年長児たちも気づかなかった大発見になりました。今日の活動を見ていると、私たち教師では教えきれないものを子どもたちは発見し、それを自分たちで解決していきます。私たちはそんな子どもたちの手助けを少ししてあげることが大切なのだと改めて考えさせられたのでした。
最近、ひまわり組ではごっこ遊びが盛んになっています。9月末に初めて絵本の貸し出しを経験した子どもたちは、たくさんの絵本の中から自分の好きな絵本を借りることができたことがとても嬉しかったようでした。今日も給食台の上に、たくさんの絵本を並べて本屋さんごっこが始まりました。「いらっしゃいませ。」「どれにしますか?」と店員さんとお客さんになって楽しんでいました。Sくんは、絵本を買うためにはお金が必要だということに気づくと、裏紙にパステルで丸や数字を書き始めました。お金のやり取りもできるようになったことで、本屋さんごっこはさらに楽しくなっているようでした。
コメント (「ちょっとした手助けの大切さ」 ひまわり組 丸山利夫 はコメントを受け付けていません)




















































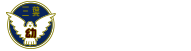

コメント (「春が来た♪どこに来た♪」(3学期終園式&お別れ会) ひまわり組 丸山利夫 はコメントを受け付けていません)